| �؈ޏk�������d���ǁiALS�FAmyotrophic Lateral Sclerosis�j |
�P�F�؈ޏk�������d���ǁiALS�j�̊T�O
�i�P�jALS�Ƃ�
�@�@�@�@��ʉ^���j���[�����Ɖ��ʉ^���j���[�����̗��҂��זE��(���邢�͊j����)���U�����E�i�s���ɕϐ��E������
�@�@�@�@�_�o�ϐ������ł��B
�@�@�@�@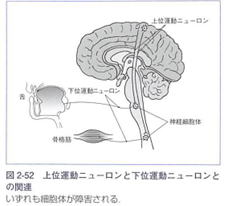 �@ �@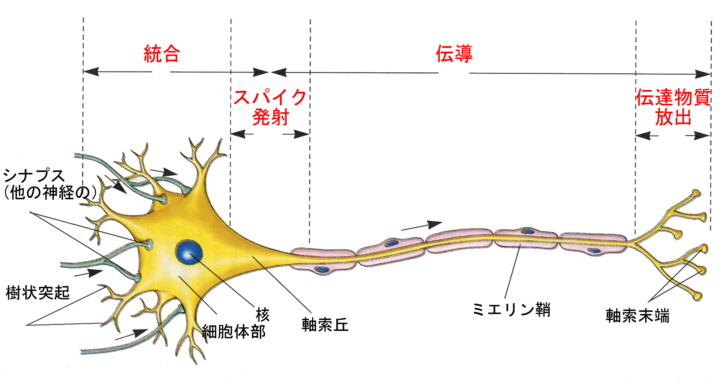
�i�Q�jALS�̓���
�@�@�@�@�^���j���[�����̍זE�݂̂̂���Q���A����ɂ��]����̎w�߂��`�B����Ȃ���ԂƂȂ�܂��B
�@�@�@�@���̂��߁A�ؗ͒ቺ��؈ޏk�������A�₪�Ď��Ɏ���܂��B
�@�@�@�@���̈���ŁA�̂̊��o�A���͂⒮�́A�����@�\�Ȃǂ͂��ׂĕۂ�������Ƃ����ʂł��B
�@�@�@�@
�@�@�@�@
�i�⑫�j�]�E�_�o�E�؎����̕���
�@A-�_�o�ϐ�����
�@�@�@�@�P�F�p�[�L���\���a�@�@�Q�F�Ґ����]�ϐ��ǁ@�@�@�R�F�؈ޏk�������d����
�@B-�_�o�ؐڍ��������@�@ �@�@�@
�@�@�@�@�P�F�d�Njؖ��͏�
�@C-�؎���
�@�@�@�@�P�F�W�X�g���t�B�[��
�@D-���쐫�_�o���� �@�@ �@
�@�@�@�@�P�F��
�Q�FALS�̕���
�@�@�@�@ALS�́A�i�s���́A��ʁE���ʘA���j���[������Q���A�����̐g�̕��ʂŔF�߂邱�Ƃ���{�ł��B
�i�P�j��ʁE���ʉ^���j���[�������Ƃ��ɂ݂������
�@�@�ÓT�^
�@�@�@�@��ʁE���ʉ^���j���[�������l���E�̊��E�]�_�o�̈�ɐi�W���́B
�@�A�i�s������^
�@�@�@�@�a�����ɔ]�_�o�̈�ɋ�����l���ɂ͂��܂�ڗ����Ȃ�
�i�Q�j��ʉ^���j���[����������������� �@�@
�@�@�i�s���؈ޏk��
�@�@
�@�A�t���C���A�[���ifrail arm�j�^
�@�@�@�@���㎈�Ɍ��ǂ�����̂ł��B
�@�@
�@�B�t���C�����b�O�ifrail leg�j�^
�@�@�@�@�������Ɍ��ǂ�����̂ł��B
�i�R�j���ʉ^���j���[����������������� �@�@
�@�@��ʉ^���j���[�����^ �@�@
�@�A�����������d���� �@�@
�@�BMills���^
�@�@�@�@�ꑤ�㉺����N���A�z���Ж�����悷�鈟�^�B �@
�i�S�j���̑� �@�@
�@�@�F�m�ǂ�ALS�iALS-D�j �@�@
�@�@�@�@���炩�ȔF�m�ǂ��݂���Ǘ�͂��悻2�����x�ł���A�a���̐i�s�ƂƂ��ɔ䗦���������܂��B
�@�A�ċz�،^
�@�@�@�@�ċz���Ȃ���n�܂鈟�^�ł��B
�@�@�@�@�؈ޏk�������d���ǂ̖�3���Ōċz�s�S�������Ǐ�ƂȂ�A���̑������㎈�̒E�͂����Ă��܂��B
�@�@�@�@�����s���̍S�������C��Q�̌��������̂ЂƂɋ؈ޏk�������d���ǂ��������܂��B
�R�F���� �@�@
�i�P�j����
�@�@�@�@�m��I�Ȍ����͕s���ł��B�@
�@�@�@�@�_�o�̘V���Ɗ֘A������Ƃ����Ă��܂��B
�@�@�@�@����ɂ͋������A�~�m�_�̑�ӂɈُ킪����Ƃ̊w����t���[���W�J���̊֗^������Ƃ̗l�X�Ȋw��������܂����A
�@�@�@�@���_�͏o�Ă��܂���B
�i�Q�j�a��
�@�@�@�@���݂܂łɎ��̂悤�ȕa�Ԃ����炩�ɂ���Ă��܂��B�@�@�@�@
�@�@�@�@�_�o�̘V���Ƃ̊֘A�A�������A�~�m�_�̑�ӈُ�A�_���X�g���X�A�^���p�N���̕�����Q�A
�@�@�@�@���邢�̓~�g�R���h���A�̋@�\�ُ�Ƃ��������܂��܂Ȋw��������܂��B
�@�@�@�@�Ƒ��� ALS�ł�20���錴����`�q�̕ω����������Ă��܂��B
�@�@�@�@���{�l�̉Ƒ���ALS�ł́A�X�[�p�[�I�L�V�h�E�f�B�X���^�[�[�iSOD1�j��`�q�Ɍ��������邱�Ƃ������Ƃ�����
�@�@�@�@�i��2���j�A���̂ق�FUS�CTARDBP�CVCP�COPTN�Ƃ�������`�q�Ɗ֘A����ꍇ������܂��B
�@�@�@�@����A���ẲƑ���ALS�ł�C9ORF72�Ƃ�����`�q�Ɍ���������Ⴊ�����A�l��⍑�ɂ��Ⴂ���w�E����Ă��܂��B
�S�F�u�w �@�@
�i�P�j�L�a��
�@�@�@�@���{�ɂ�����ALS�̗L�a���F�P�`2.5�l�^10���l
�@�@�@�@�S���ł���P���l�̊��҂����܂��B �@�@
�@�@�@�@�Ƒ�����ALS�̊�����5.1%�ʂł��B �@�@
�i�Q�j�����E�D���N��
�@�@�@�@�j���䁁1.3�`l.4�F1�@�j���ɂ�⍂���B �@�@
�@�@�@�@���ǔN�60�`70���ł������B
�i�R�j��`��
�@�@�@�@���e�̂����ꂩ���邢�͂��̌Z��A�c����Ȃǂɓ����a�C�̂ЂƂ����Ȃ���A��`�̐S�z������K�v�͂���܂���B
�@�@�@�@���̈���ŁA�S�̂̂Ȃ��̂��悻5���͉Ƒ����Ŕ��ǂ��邱�Ƃ��������Ă���A�Ƒ���ALS�ƌĂ�Ă��܂��B
�@�@�@�@���̏ꍇ�͗��e�̂����ꂩ���邢�͂��̌Z��A�c����Ȃǂɓ����a�C�̂ЂƂ����邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B
�T�F�Ǐ�
�@�@�@�@�؈ޏk�������d���ǂ́A�葫�E�̂ǁE��̋ؓ���ċz�ɕK�v�ȋؓ������X�ɂ₹�ė͂��Ȃ��Ȃ��Ă����a�C�ł��B
�@�@�@�@���ʉ^���j���[�����Ǐ�A��ʉ^���j���[�����Ǐ�A����Ǐ�A�F�m�@�\��Q�A�A�����m���Ă��܂��B
�i�P�j�����Ǐ� �@
�@�@�@�@���Ǘl���ɂ��قȂ�܂����A�㎈�^(���ʌ^)�ł͏㎈�̋؈ޏk�Ƌؗ͒ቺ����̂ƂȂ�܂��B �@
�@�@�@�@��w�̓������ɂ�����I�����̗͂��キ�Ȃ�A�ؓ����₹�邱�Ƃ���n�܂�܂��D
�i�Q�j�Ǐ�̃^�C�v
�@�@�㎈�^�i���ʌ^�j
�@�@�@�@�㎈�̋؈ޏk�Ƌؗ͒ቺ����̂ŁA�������z�k�������܂��B
�@�@�@�@�S�g�̋ؗ͒ቺ�A�؈ޏk�A�@�ۑ������k�i�ؓ��������݂��z������j
�@�A���^�i�i�s���������j �@
�@�@�@�@�ېH������Q�A�����Q�Ȃǂ̋��Ǐ�̂ƂȂ�܂��B�@
�@�@�@�@�b���ɂ����A�H�������ݍ��݂ɂ����Ƃ����Ǐ�n�܂�܂��B
�@�@�@�@��̈ޏk�������ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@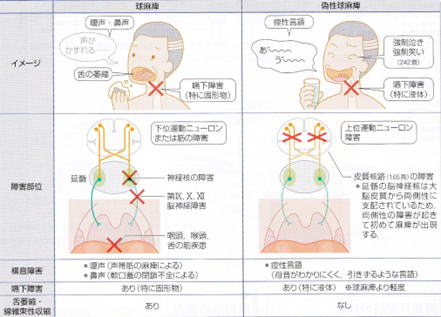
�@�@�@�@�w�a�C���݂��� �qvol.7�r �]�E�_�o�x������p
�@�B�����^�i�U�����_�o���^�j
�@�@�@�@�������甭�ǂ��A�������F���˒ቺ�E��������������݂��A�^���j���[�����̏�Q���O�ʂɏo��^�ł��B
�@�@�P�j�F���˘��i
�@�@�@�@�@�@�������i�ɂȂ����F�����o�ɂ�����ԂŌy���n���}�[�Œ@���ƁA��u�x��ċ��s���ӂɎ��k���锽�˂ł��B
�@�@�@�@�@�@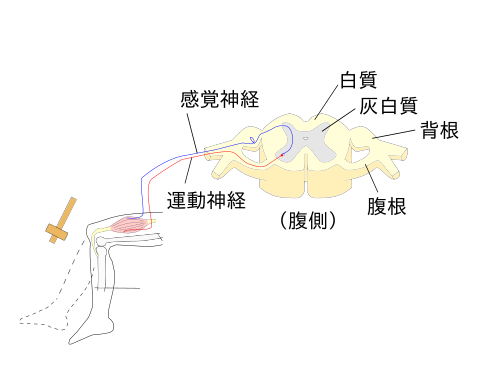
�@�@�@�Q�jBabinski����i�{�j
�@�@�@�@�@�@�a�I���˂̈��ŁA���̗��̊O���i���w���j������������Ƒ��̐e�w���b�̕��ɔ���Ґ����˂̈�ł��B
�@�@�@�@�@�@����3�������炢�܂ł̐V�����Ō����܂����A����ȍ~�̌���҂ɂ͌����܂���B
�@�@�@�@�@�@���Ӊ^�����x�z���鐍�̘H�ɏ�Q���N����ƌ����܂��B
�@�@�@�@�@�@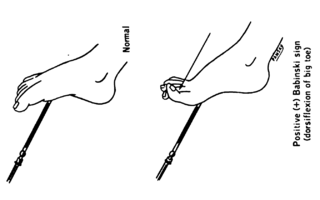
�U�F�\��
�i�P�j�o��
�@�@�@�@�Ǐ�̐i�s�͔�r�I�}���ŁA���ǂ��玀�S�܂ł̕��ϊ��Ԃ͖�3.5�N�Ƃ����Ă��܂����A���m�Ȓ����͂Ȃ��A
�@�@�@�@�l�������ɑ傫���ƌ����Ă��܂��B
�@�@�@�@�i�s�͋���^���ł������Ƃ���A���ǂ���R�����ȓ��Ɏ��S����������܂��B
�@�@�@�@����ł́A�i�s���x���A�ċz�⏕������10���N�̌o�߂����������A�ǗႲ�Ƃɍׂ₩�ȑΉ����K�v�ƂȂ�܂��B
�i�Q�jALS�̎��� �@
�@�@�@�@��P�ʁ��x��---14���@�@�@
�@�@�@�@��Q�ʁ��O��---4.4���@�@�@
�@�@�@�@��R�ʁ��S��~�E���s�S---3.4�� �@
�@�@�@�@��S�ʁ�����---3��
�V�F���Ö@
�@�@�@�@�����Ö@�͂Ȃ��A�ΏǗÖ@�����S�ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@���\�]�[���i�O���^�~���_�h�R��j�ɂ��Ö@�Ő������Ԃ�����������ʂ�����܂��B
�i�P�j�Ö@ �@
�@�@�a���i�W��}�� �@�@
�@�@�@�@���\�]�[���݂̂�ALS���Ö�Ƃ��Đ�������Ă��܂��B �@
�@�@�@�@���\�]�[���i���i���������e�b�N��50�j
�@�@�@�@�@�@�_�o�`�B�����̃O���^�~���_��t���[���W�J���ȂǂɊւ��A�_�o�זE�̏�Q��}���邱�Ƃ�ALS�̐i�s��
�@�@�@�@�@�@�x�点���ł��B
�@�A�s����}���� �@�@�@
�@�@�@�@�R�s�������R������p���܂��B �@
�@�B�z�k���������ꍇ �@�@�@
�@�@�@�@�R���������p���܂��B �@
�@�C�ɂ݂ɑ��� �@�@�@
�@�@�@�@���ɖ�⎼�z���p���܂��B
�i�Q�j���̑��̗Ö@ �@�@
�@�@�e�߂̍S�k�\�h �@�@�@
�@�@�@�@���n�r���e�[�V�������d�v�ƂȂ�܂��B �@�@
�@�A�ċz��Q�ɑ��� �@�@�@�@
�@�@�@�@�ċz�̌P����P��A�r�o�⏕�Ȃǂ̌ċz���w�Ö@�ɂ��Ή����s���܂��B
�@�@�@�@�a��̐i�s�ɂ��A�C�ǐ؊J�ɂ��N�P�I�Ȍċz�⏕�Ö@���s���܂��B�@�@
�@�B�ېH������Q���i�s�����ꍇ �@�@�@�@
�@�@�@�@�K�v�ɉ����Čo�@�o�ljh�{�A�ݑ����ݏp�Ȃǂ��l�����܂��B
�@�@�@�@�܂��A�뚋�h�~�̂��߂̎�p�i������p�E�C�ǍA�������p�E�A���E�o�p�j���s���邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�@�@
�@�C�R�~���j�P�[�V�����̊m�� �@�@�@�@
�@�@�@�@�Ǐ�̐i�s�ɂ�蔭��@�\���ω����Ă������߁A���߂ɐV���ȃR�~���j�P�[�V������i���m������K�v���L��܂��B
|
| ALS�Ǝ��Ȉ�� |
�i�P�j���o�Ǐ� �@�@
�@�@��ʉ^���j���[������Q�̒��� �@�@�@�@
�@�@�@�@����炵���� �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@���{���˂̏[�i��A���O�̎�����y���@�ł���ƌ������ڂߓ˂��o���@�@�@
�@�@�@�@�\����Q �@�@�@�@
�@�@�@�@�ېH������Q
�@�A���ʉ^���j���[������Q�̒��� �@�@�@�@
�@�@�@�@�����w�i�����̉^���_�o�j�Z�A�\�AX�A�I�U�̖�Ⴡj�ɔ����A�ȉ��̏Ǐ����ł��B
�@�@�@�@��A�����A���W�ɂ�����̋ؗ͒ቺ �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@��ޏk �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�A���̐��ۑ������k�ɂ��^����Q �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@��Q�A�ېH������Q�A�\����Q
�@�@�@�@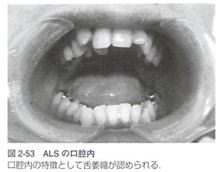
�@�BALS�̌ċz�s�S�ƚ�����Q
�@�@�@�@�ċz�s�S�ƚ�����Q�͕��s���Ĉ������Ă����܂��B
�@�@�@�@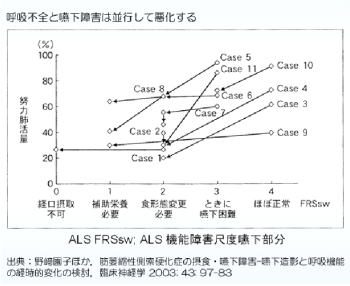
�@�CALS�̐ېH������Q
�@�@�@�@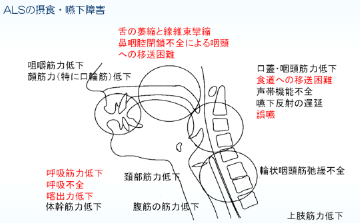
�i�Q�j���Ȏ��Î��̒��ӓ_
�@�@�Ԃ�����X�g���b�`���[�ɂ�闈�@�̏ꍇ �@�@
�@�@�@�@�f�Î����ł͈ړ��̍ۂ̓����ɔz�����A�ړ��̏�Q�ɂȂ���̂����炩���ߔr������K�v���L��܂��B�@�@
�@�@�@�@���Â����ւ̈ڏ��K�v�Ƃ���ꍇ�A�����̉�҂ɂ�萺���������Ȃ���ڏ���s���ƈ��S�ł��B
�@
�@�A�g�̜̂]�Ȃ�ό`��F�߂�ꍇ �@�@
�@�@�@�@�f�Ñ̈ʂƎp���̃R���g���[�����K�v�ł��B
�@�@�@�@�^�I����N�b�V�����ȂǂŐg�̂Ɛf�Ñ�ߑ̊������肳���A�x���g�ɂ��ے肷��Ȃǂ̍H�v���K�v�ł��B
�@�B�C�ǐ؊J��l�H�ċz������Ă���ꍇ �@�@
�@�@�@�@�ʉ@����ƂȂ�A�K�⎕�Ȑf�ÂőΉ����邱�Ƃ������Ȃ�܂��B �@�@
�@�@�@�@�o�C�g�u���b�N�ɂ��ċz�}���ɒ��ӂ����Ƃ���ł��B�@�@
�@�@�@�@���o�[�_���h�����ł̊m���ȃo�L���[������A�z�����v������܂��B�@�@
�@�@�@�@�p���X�I�L�V���[�^�[���g�p�����o���I�_�f�O�a�x�̑�������{���鎖���d�v�ł��B �@
�@�@�@�@
�@�C���̑� �@�@
�@�@�@�@���炩���ߊ��҂��\�o�ł���T�C�����m�F�̂����A���Ȏ��Â�i�߂Ă����܂��B �@�@
�@�@�@�@���o���|�́A���X�ɕ������S��ƂȂ邽�߁A�a��ɉ���������K�v�ƂȂ�܂��B�@�@
�@�@�@�@���Ɍ뚋���x���\�h�̂��߂̊펿�I�P�A�͏d�v�ł��B
�@�@
�@�@�@�@���o���͋̋@�\�ێ��̂��߂ɊԐڌP�����������܂���B
�@�@�@�@�@�@�ߌP��---����P���iROM)��J���P���Ȃ� �@�@
�@�@�@�@�h�{��Ԃ̕]���̂��ƁA�H���e�Ȃ�тɐH�`�Ԃ̌������d�v�ƂȂ�܂��B
�@�⑫�F�C�ǃJ�j���[�����g�p���Ă�����ւ̒��ӎ���
�@�@�@�@�C�ǃJ�j���[�����g�p���Ă�����C�Ǔ����肪�ł��₷���Ȃ��Ă��܂��B
�@�@�@�@���̂��ߓ��肩��̏o����A�r����������̏o�����X�N������܂��B
�@�@�@�@�C�ǃJ�j���[���ɐG��Ȃ������d�v�ł��B
�@�@�@�@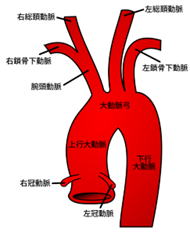 �@�@ �@�@
|
| �Q�l���� |
�@�@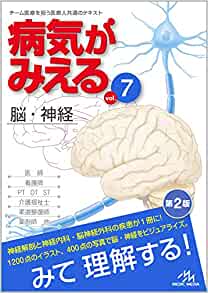 �@�w�a�C���݂��� �qvol.7�r �]�E�_�o�x �@�w�a�C���݂��� �qvol.7�r �]�E�_�o�x
|


 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@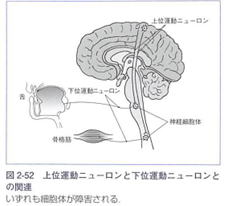 �@
�@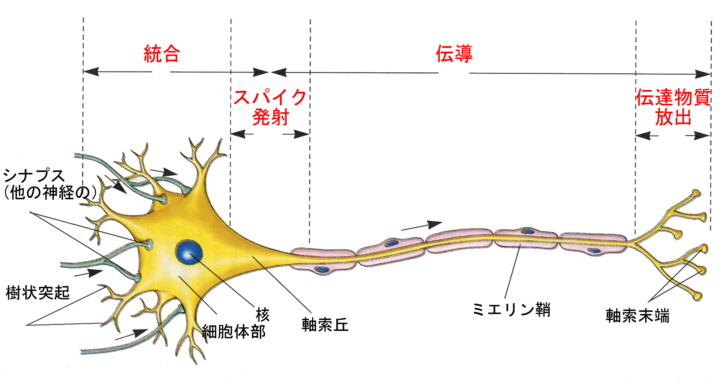

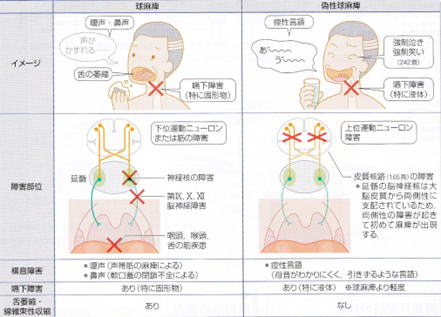
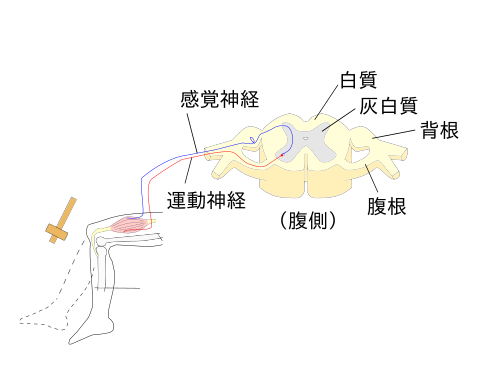
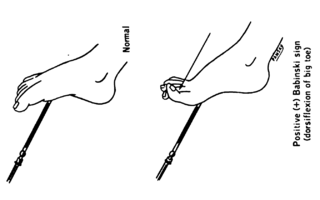

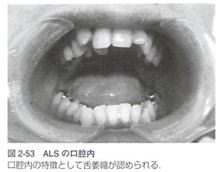
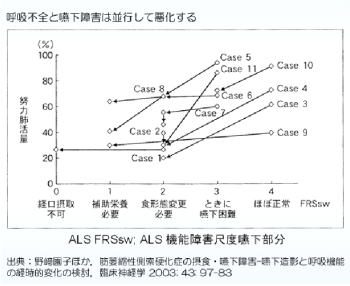
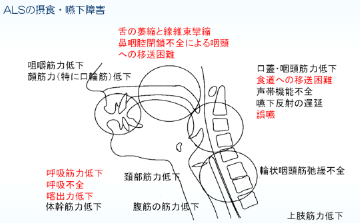

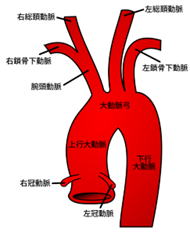 �@�@
�@�@
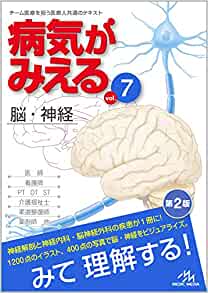 �@�w
�@�w