| ���ꎕ�ɂ��ā@�iDenture) |
| |
�P�F���ꎕ�Ƃ�
���ꎕ�Ƃ͑r����������₤�ׂ̐l�H����̑��̂ł��B
�`���i�����j�Ƃ������܂����A���̏ꍇ�ɂ͒ʏ�P���A���Ȃ킿���O�����K�v�Ȃ������w���܂��B
�`���̗��j�͋I���O�ɂ܂ők��Ƃ����Ă��܂��B
���{�ł͕�������̂���Ɏg���͂��߁A�����̗L���`���̑f�ނ́A�ؐ��ł����B
���݂́A�v���X�`�b�N�i���W���j����A��A�`�^���A�Z���~�b�N�A���^���{���h�|�[�Z�����i����j�Ȃǂ̑f�ނ��g�p����Ă��܂��B
���N�ی��K�p�̕ی��`���ƌ��N�ی��K�p�O�̋`��������A����͐f�Ó��e��`���Ɏg�p�����ޗ��̈Ⴂ�ɂ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�@�u���̔����فv���@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ쌧�@�u���̔����فv��
�Q�F���ꎕ�̎��
�L���`���ɂ�
�@�@�@�������`���i�������ꎕ�j�ƁA���`���i�����ꎕ�j������܂��B
�Ǖ����`����1����������1���c���܂ł̏Ǘ�Ɏg�p�����`���̎����������܂��B
�S�����`���͎c�������S�������Ǘ�Ɏg�p����`���̎��ł��B
�������`���́A�u���v�u�l�H���v�u�N���X�v�v�u���X�g�v�u�A���q�v������\������Ă��܂��B
�S�����`���́u�B���v�u�l�H���v�݂̂ō\������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@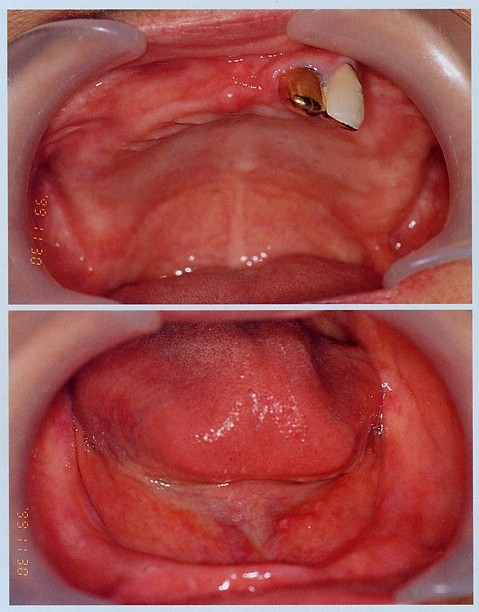 �@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��͕������ꎕ�A���͑����ꎕ
�R�F���ꎕ�̐���H��
�@�i�P�j����H���̊T�v
�@�@�@�@�@���̐}�͑�܂��ȋ`������̍H���������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@����������͂����܂ł��`���݂̂̍쐬�ߒ��ŁA�����ɂɎ���O�ɁA�c�����̎��Â�S���̒����A
�@�@�@�@�@�ꍇ�ɂ���Ă͍����N�ȂǍ��̒������K�v�Ȏ�������܂��B
�@�@�@�@�@�܂��A�����̋`���������K�{�ŁA���ꂪ�d�v�Ȏ��ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@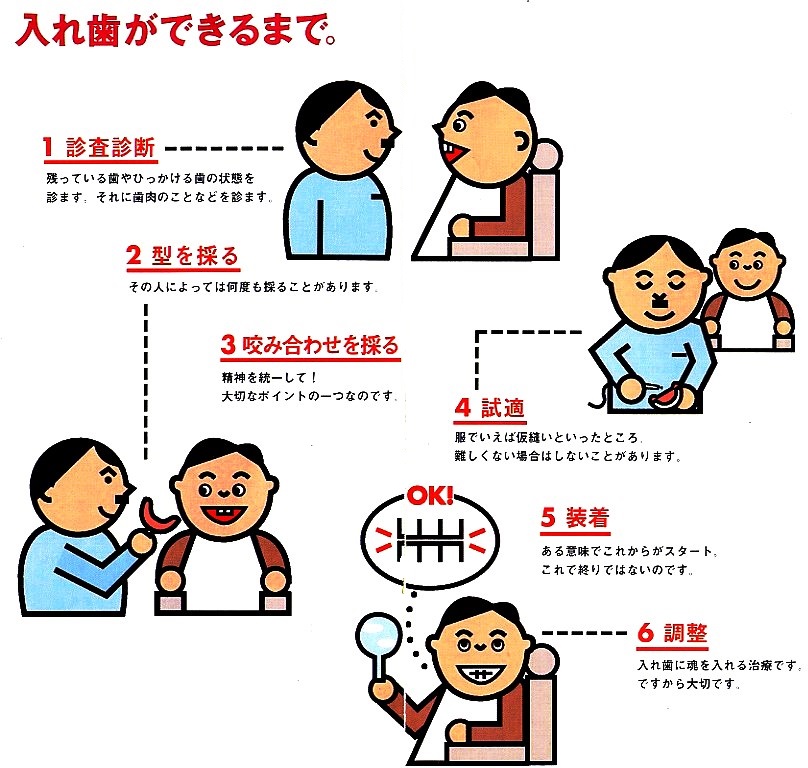
�S�F�`���̒����E��舵����
�@�@�@�`��������O�Ɂc
�@�@�@�@�悭�����������A���̒��ɐH�ׂ����������悤�ɂ��܂��B
�@�@�@�@�`���ɉ��ꂪ�t�����Ă��Ȃ����m�F���A���ȂǂŎ��点�ĉ������B
�@�@�@�@�������`���̓�����E���O�����̃R�c
�@�@�@�@�@1)������F
�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ����i��{�̕�����ʓI�Ɉ��肵�₷�����߁j�B
�@�@�@�@�@�@�@�N���X�v�̒��E�����͌����Ă��邽�߁A�܂��N���X�v���|���鎕�̈ʒu�܂Ŏ����Ă����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�`���S�̂��w�Ŏx���A���E�����ɉ����Čy���������A�������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�����ċ`�������œ���Ȃ����ƁB�N���X�v�̕ό`��A�j���̌����ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�����ȋ`���́A�������莝���Č뚋�̂Ȃ��悤�\�����ӂ��Ă��������B
�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F
�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�l�����w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���A�e�w�����̏�ɒu���A�l�����w���� �������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A�e�w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���l�����w�����̏�ɒu���A�e�w�������グ�܂��B
�@�@�@�A�S�����`���̓�����E���O�����̃R�c
�@�@�@�@�@1)������F
�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�`���̒��������w�ʼn������z��������B
�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A����̐l�����w�����E�̎��̏�ɒu���A�e�w���{�̉��ɓY���o���̎w�ł͂��ނ悤�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�`�������肷��܂Ōy�������ɉ�������B
�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F
�@�@�@�@�@�@�@�`���̒[�Ɏw�������Ă͂����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@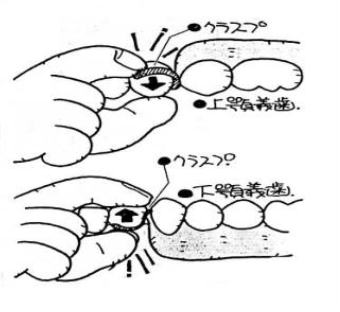
�@�@�@�B�`���̎����
�@�@�@�@�@�@�`���̉���́A�ۂ̑��B�ɂ���Ď����̉��ǁA�������̒����A���L�̌����ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�`���͖��H��ɂ͂����A���|���s���܂��B
�@�@�@�@�@�@���ɗ[�H��E�A�Q�O�̐��|���d�_�I�ɍs���܂��B
�@�@�@�@�@�@�`���̕\�ʂɏ���t���Ȃ��悤�y���͂Ő��|���܂��B
�@�@�@�@�@�@�����܂͌����܂��܂ނ��̂�����A�`���������邱�Ƃ�����g�p�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B
�@�@�@�@�@�@���ꎕ���܂̎g�p�͌��ʓI�����A�K���u���V�ł̐��|��Ɏg�p���Ă��������B
�@�@�@�C�c�����̎����
�@�@�@�@�@�@�������̂�����́A�P�{�ł����������c���w�͂��̐S�ł��B
�@�@�@�@�@�@���ɁA���ꎕ�ɐڂ��Ă��鎕�͉��ꂪ�t�����₷���̂Œ��J�ɐ��|����K�v������܂��B
�@�@�@�D�`���̕ۊǕ��@
�@�@�@�@�@�@�`���̍ޗ��ł��郌�W���͋z������L���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���O�����Ƃ������������Ȃ����Ƃ���ł��B
�@�@�@�@�@�@��������Ƌ`���ɘc�݂��A�K���������Ȃ�����A����錴���ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�`�����|��A�ۑ��p�e��ɐ������`����Z���Ă����܂��B
�@�@�@�E��Ԃ̑Ή��ɂ���
�@�@�@�@�@�����Ƃ��Ė�Ԃ͋`�������O�����ƁB
�@�@�@�@�@�q�� �R�r
�@�@�@�@�@�@�@�ۂ̑��B�i�J���W�_�ۂȂǁj��h���B
�@�@�@�@�@�@�@�`���͊�{�I�ɔS�����S�ł��邽�߁A���O�����ƂŔS���̌��s���͂���B
�@�@�@�@�@�������A���ݍ��킹���s����ȏꍇ��A�c�����������Ȃ��Ď������������Ȏ��ɂ́A��Ԃ��������Ă��������B
�@�@�@�@�@�������A�K���A�Q�O�Ɏ��Ɠ��ꎕ�̐��|�����鎖���K�v�ł��B
|
| �������`���@�iPatial�@Denture�j |
| |
�P�F�������`���Ƃ�
�����I�Ȏ��̑r����₤�ׂɗp�����鎕������ԑ��u�̎��ł��B
��ʂɂ͕������ꎕ�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B
���o�S���x���݂̂̑��`���Ƃ͈Ⴂ�A�c���Ă��鎕�ɂ��x�������߂�`�����w���܂��B
�Q�F�\��
�@�i�P�j����
�@�@�@�@�@���o�S���ɐڂ��镔���̂��ƂŁA���W��������ō���Ă��܂��B
�@�i�Q�j�l�H����
�@�@�@�@�@�{���V�R�������������ŁA�l�H�������ׂ��Ă��镔���ł��B
�@�@�@�@�@���W�����ⓩ���A�������Ȃǂ��g���Ă��܂��B
�@�i�R�j�ꕔ�F�N���X�v (clasp)
�@�@�@�@�@���o���Ɏc�����鎕�ɕ������ނ悤�Ɋ|�����邱�ƂŁA�Ǖ����`�������肳���܂��B
�@�@�@�@�@�܂��b�����|�����鎕���b���i�������j�Ƃ����܂��B
�@�@�@�@�@�N���X�v�́A�����������̓��C���[���Ȃ��Đ��삳��܂��B
�@�@�@�@�⑫�F�A�Z�^���N���X�v�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�z���C�g�N���X�v�Ƃ��Ă�A�M�Y�����W���̃A�Z�^����p�����N���X�v�̂��Ƃł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����F���Ő��삪�ł��邽�ߐR���I�ɗD�ꂽ�N���X�v���쐬���鎖���ł��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���̐F���Ǝ����F�ƈ�v�����R���I�ɕ�Ԃ��ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@���^���N���X�v�ƈႢ�ɂނ��Ƃ����A10���E���Ă��ό`�E���Ղ͂قƂ�ǂȂ��Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���^���N���X�v�����J���ł��蒷���Ԃ̑����ł����K�Ɏg����Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�_������邽�ߑ����̕��S�����Ȃ��̂ł����A�j�܂̉\�����L��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�������A������g���ƁA�S�Ă��ی��K���O�ƂȂ�܂��B
�@�i�S�j��A���q
�@�@�@�@�@���L�̉摜�̌�����������U�������́A��A���q�̈��̃p���^���o�[�ƌ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�R�F����ȕ������`��
�@�i�P�j�e���X�R�[�v�f���`���[
�@�@�@�@�@�e���X�R�[�v�f���`���[�Ƃ́A�ێ����u���N���X�v�i�ˁj�ł͂Ȃ��A�͂ߍ��ݎ��̋@�\��p�����`���̑���
�@�@�@�@�@�ł��B
�@�@�@�@�@������̃^�C�v���ی����K�p����Ȃ����R�f�ÂƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@��\�I�Ȃ��̂ɁA�R�[�k�X�N���[�l��[�Q���e���X�R�[�v�Ȃǂ�����܂��B
�@�@�@�@�@���Ȃ݂Ƀe���X�R�[�v�Ƃ́u�]�����v�i�����j�ł͂Ȃ��A�u�͂ߍ��ݎ��́v�Ƃ����`�e���ł̈Ӗ��ł��B
�@�i�Q�j�R�[�k�X�N���[�l
�@�@�@�@�@�ێ����u�Ƃ��ăN���X�v�i�ˁj���g�킸�A��d�\���łł��������g�����Ƃߍ��ݎ��̋@�\��p�����`���̎�
�@�@�@�@�@�ł��B
�@�@�@�@�@�e���X�R�[�v�f���`���[�̈��ŃR�[�k�X�A�R�[�k�X�e���X�R�[�v�A�������`���Ƃ��Ă�܂��B
�@�@�@�@�@�N���[�l�Ƃ̓h�C�c��ŃN���E���i���j�̂��Ƃŋ��`�I�ɃR�[�k�X�N���[�l��p�����`���̈ێ����u�݂̂�
�@�@�@�@�@�w�����Ƃ�����܂��B
�@�@�@�@�@�x��ƂȂ鎕���`�����A���̏�ɔ킹������̓������쐬���A���̓����ɓK������O����g�ݍ��`����
�@�@�@�@�@�쐬���܂��B
�@�@�@�@�@���̓����ƊO���̎��ʂ�6�x�̃e�[�p�[��t�^���Ă��̐ڐG�ɂ�門�C�͂𗘗p���Ĉێ����u�Ƃ��A�`����
�@�@�@�@�@�Œ肵�܂��B
�@�@�@�@�@�R�[�k�X�N���[�l�̗����͒��t�����钃�����C���[�W����ƕ�����₷���B
�@�@�@�@�@�����͖{�̂������U���Ă��W�͊O��Ȃ����A�W�ɂ������Ƃ����͂�������ƊȒP�ɊO��܂��B
�@�@�@�@�@�R�[�k�X�N���[�l�����������𗘗p���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�ی����K�p����Ȃ����R�f�ÂƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@
�@�i�R�j�m���N���X�v�f���`���[
�@�@�@�@�@�����̃o�l������Ȃ��������`���ł��B
�@�@�@�@�@�����ځi�R�����j���d�������`���ƌ����܂��B
�@�@�@�@�@�S�ĕی��K���O�ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@���t����p�̕��ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�⑫�F�������`���̌����l���ɂ�镪��
�@�i�P�j�P�l�f�B�[����
�@�@�@�@�@�T���F�������V���[����---�������鎕�̌���ɗ������̌��������݂������
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���
�@�@�@�@�@�U���F�Б����V���[����---�������鎕�̌���ɕБ����̌��������݂������
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���
�@�@�@�@�@�V���F�Б������Ԍ���---�Б��������̈�̑O���ƌ���̗����Ɏ������݂������
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���
�@�@�@�@�@�W���F�O�������Ԍ���---�������鎕�̑O���ɐ��������z���Ĉ�̌����̈��������
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv��� �@�@Wikipedia�@�u�P�l�f�B�[���ށv���
�@�i�Q�j�A�C�q�i�[�̕���
�@�@�@�����x����ɂ�鎕�̕��ޖ@
�@�@�@�@�@A�Q�F4�̙����x�����S�Ď�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@A1�F�����C���̂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@A2�F�㉺�{�̂���1�{�̂ݎ��匇������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@A3�F�㉺�{�Ƃ������L��
�@�@�@�@�@B�Q�F�����x���悪������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@B1�F3�̎x���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@B2�F2�̎x���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@B3�F1�̎x���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@B4�F�x���悪�Ȃ�(�O�����݂̂ə����ڐG������)
�@�@�@�@�@C�Q�F�����x���悪�Ȃ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@C1�F�㉺�{�Ɏc����������(����Ⴂ����)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@C2�F�㉺�{�̂���1�{�������{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@C3�F�㉺�{�Ƃ������{
|
| �S�����`���@�iFull�@Denture�@�܂��́@Complete�@Denture�j |
| |
�P�F�������`���Ƃ�
��������ԑ��u�̂����A�����{�҂ɂ�����́A���Ȃ킿��{�����������l�̓��ꎕ�ł��B
�����ꎕ�Ƃ������܂��B
�Q�F�\��
�@�i�P�j�l�H����
�@�@�@�@�@�{���V�R�������������ŁA�l�H�������ׂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@���W�����ⓩ���A�������Ȃǂ��g���܂��B
�@�i�Q�j����
�@�@�@�@�@�l�H�����ȊO�̕����������Ƃ����܂��B
�@�@�@�@�@�ʏ�̓��W���������̓X���t�H���݂̂ō���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@
�R�F����ȑS�����`��
�@�i�P�j�������`��---�ی��K�p���O
�@�@�@�@�@�S���ʂ���W���A�㑤�ȂNJO�ςɐG��Ȃ��������R�o���g�A�`�^���A���Ȃǂō��A�ٕ��������Ȃ��A
�@�@�@�@�@�H�������R�ȉ��x�Ŗ��킦��l�ɂ������ꎕ�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@
|
| ���ꎕ�Ɋ֘A����O�b�Y |
�@
�@�`�����܁@�@�`���p�u���V
�@�`�������
|
| ��ʌ��� |
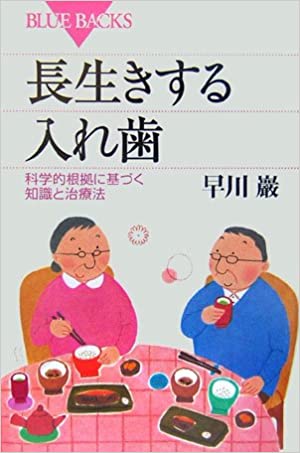 �@�w������������ꎕ�\�Ȋw�I�����Ɋ�Â��m���Ǝ��Ö@ (�u���[�o�b�N�X) �x �@�w������������ꎕ�\�Ȋw�I�����Ɋ�Â��m���Ǝ��Ö@ (�u���[�o�b�N�X) �x
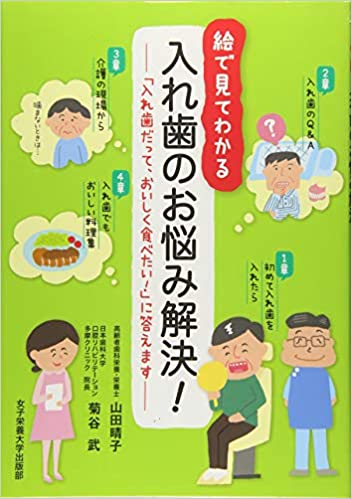 �@�w�G�Ō��Ă킩����ꎕ�̂��Y�݉���!�x �@�w�G�Ō��Ă킩����ꎕ�̂��Y�݉���!�x
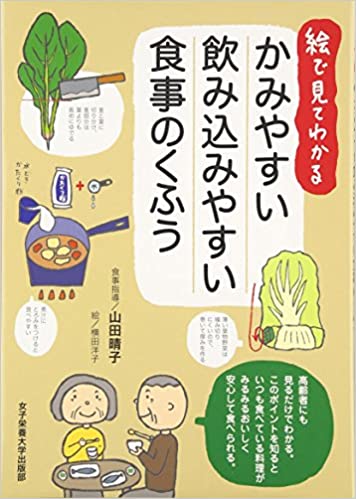 �@�w���݂₷�����ݍ��݂₷���H���̂��ӂ��\�G�Ō��Ă킩���x �@�w���݂₷�����ݍ��݂₷���H���̂��ӂ��\�G�Ō��Ă킩���x
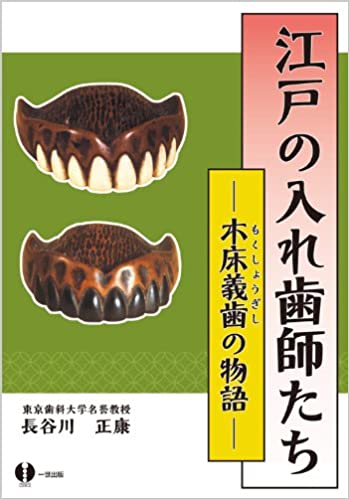 �@�w�]�˂̓��ꎕ�t�����@���؏��`���̕����x �@�w�]�˂̓��ꎕ�t�����@���؏��`���̕����x
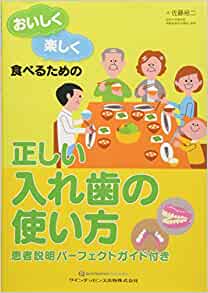 �@�w���������y�����H�ׂ邽�߂� ���������ꎕ�̎g�����x �@�w���������y�����H�ׂ邽�߂� ���������ꎕ�̎g�����x
|
| �Q�l����-���ȊW�җp |
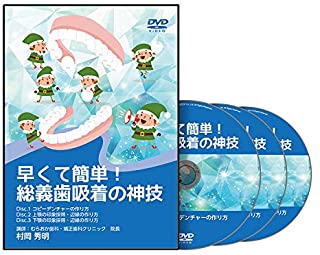 �@�w�����ĊȒP�I���`���z���̐_�Z�x�@�@���� �G�� �@DVD �@�w�����ĊȒP�I���`���z���̐_�Z�x�@�@���� �G�� �@DVD
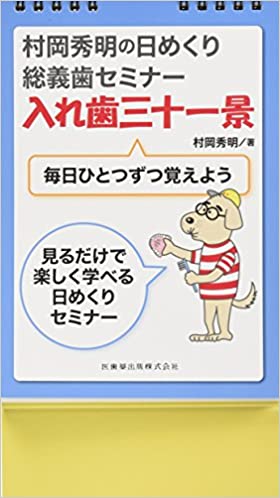 �@�w�����G���̓��߂��葍�`���Z�~�i�[�@���ꎕ�O�\��i�@�����ЂƂ��o���悤 �J�����_�[�x �@�w�����G���̓��߂��葍�`���Z�~�i�[�@���ꎕ�O�\��i�@�����ЂƂ��o���悤 �J�����_�[�x
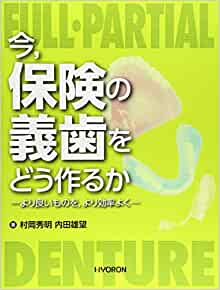 �@�w��,�ی��̋`�����ǂ���邩: ���ǂ����̂�,�������悭�x �@�w��,�ی��̋`�����ǂ���邩: ���ǂ����̂�,�������悭�x
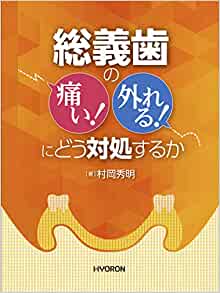 �@�w���`���́u�ɂ�! �v�u�O���! �v�ɂǂ��Ώ����邩�x �@�w���`���́u�ɂ�! �v�u�O���! �v�ɂǂ��Ώ����邩�x
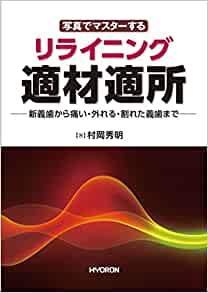 �@�w�����C�j���O�K�ޓK���x�@�����G���@�q���[�����E�p�u���b�V���[�Y �@�w�����C�j���O�K�ޓK���x�@�����G���@�q���[�����E�p�u���b�V���[�Y
 �@�w������Љ�ɂ�����h���C�}�E�X�ւ̑Ή��x �@�w������Љ�ɂ�����h���C�}�E�X�ւ̑Ή��x
|



