| 強迫症(OCD:Obsessive compulsive disorder) |
1:強迫症
(1)強迫症とは
きわめて強い不安感や不快感(強迫観念)をもち、それを打ち消すための行為(強迫行為)を繰り返す病気です。
強迫症の症状を強迫症状といいます。
強迫症状には、強迫観念と強迫行為があり、このふたつが存在して初めて強迫症と診断されます。
(2)病因
強迫症では、その原因や発症にかかわる特異的な要因はいまだ特定されていません。
対人関係や仕事上のストレス、妊娠・出産などのライフイベントが発症契機となりうる
これらと,何らかの脆弱性要因(脳の生物学的素因など)、あるいは性格など心理的要因との相互作用を介し、
発症に至るものと考えられている.
(3)疫学
生涯有病率は約2~3%です
男女比はほぼ同等です。
平均発症年齢は約20歳です。
(4)症状
①確認(checking)
例---閉め忘れを心配して、ガス栓、玄関、窓などが正確に閉まっているかの確認を繰り返してしまう。
②汚染/洗浄(washing)
例---トイレのあと,なかなかきれいになった気になれず、手洗いやシャワーを繰り返してしまう。

③数唱(counting)
例---眼についた数字が気になって、数えてしまうのがやめられない。
(5)診断
①検査
必要に応じてY-BOCS(Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale)などの心理検査を補助的に併用します。
エール・ブラウン強迫性尺度(Y-BOCS)
強迫性障害(OCD)症状の重症度を評価するためのテストです。
②診断基準
DSM-5の診断基準をもとにします。 .
DSMはその診断の過程で、熟練した医師により、診断基準の一つとして使用されるものです。
一般の人がDSMの診断基準を見て、安易に自己診断をすることはできません。
(6)治療
①薬物療法
強迫症の主要な治療はSSRIを中心とした薬物療法になります。
②心理療法
認知行動療法も併用されます。
①薬物療法
SSRIとSNRIが第一選択薬となります。
うつ病よりさらに多い用量が必要となります。
②認知行動療法
(7)予後
2~30%が著明改善します。
40~50%が中等度改善します。
20~30%は症状が持続したり悪化したりする難治例もあります。
2:醜形恐怖症(身体醜形障害)(body dysmorphic disorder)
(1)概念
自分の身体のすべてないし一部の外見について欠陥があるのではないかとの信念を抱く疾患です。
その強い強迫観念から身体醜形障害はうつ病を併発する割合もかなり高いとされます。
(2)病因
遺伝的な素因や生育環境が発症に関連すると考えられています。
原因としては、うつ病や強迫性障害との関連が挙げられます。。
また自臭症などと並んで、統合失調症の前駆症状として現れる場合もあります。
脳内伝達物質のセロトニンの異常と、眼窩皮質という箇所の異常だともいわれています。
(3)疫学
発症は思春期から成人初期に起こります。
男女差は有りません。
(4)症状
他人には認識できないような些細な身体的な欠陥にとらわれます。
自分は醜いと自己完結的に苦悩する様になります。
鏡による確認、過剰な身づくろいなどを頻回に繰り返し、社会的生活に支障をきたします。
本人は自らの苦悩が不合理であることは理解しています。
しかし 自分ではそれをコントロールできない状態に陥ります。
(5)診断
DSM-5に基づき、客観的な所見にそぐわない自分の容姿に関する訴えを確認していきます。
(6)治療
①薬物治療
SSRIなどセロトニン作動薬が50%の患者で有効とされます。
②避けるべき治療
美容外科や歯科・口腔外科的治療は滅多に成功しません。
むしろ、新しい「欠点」が生じ.状況を悪化させる危険性があります。
顎矯正手術の適応には本症の鑑別が重要となります。
(7)予後
身体面へのとらわれはかなり頑固であり.精神科受診すらも難航します。
口腔外科や形成外科などの身体科を繰り返し受診しながら慢性的な経過をたどります。
二次的なうつ病や妄想的確信に至る場合もあります。
補足:心身症と神経症
(1)心身症
精神ストレスが大きく関わる身体の病気です。
心身症を治療するのは心療内科となります。
(2)神経症
病的な不安を主な症状とした精神の病気です。
神経症を治療するのは基本的に精神科となります。
不安神経症---不安障害全般となる.
パニック障害、社交不安障害、全般性不安障害、強迫性障害、身体表現性障害、
解離性障害、心的外傷後ストレス障害などが含まれます 。
|
| 参考資料 |
 『図解 やさしくわかる強迫症』 『図解 やさしくわかる強迫症』
 『身体醜形障害 なぜ美醜にとらわれてしまうのか 』 『身体醜形障害 なぜ美醜にとらわれてしまうのか 』
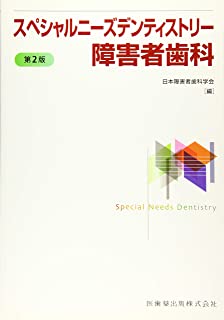 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』 『スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科 第2版』
 『DSM-5診断面接ポケットマニュアル』 『DSM-5診断面接ポケットマニュアル』
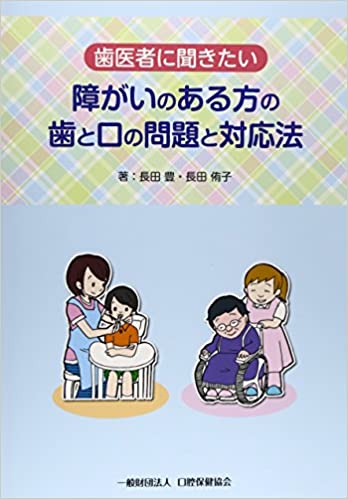 『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』 『歯医者に聞きたい 障がいのある方の歯と口の問題と対応法』
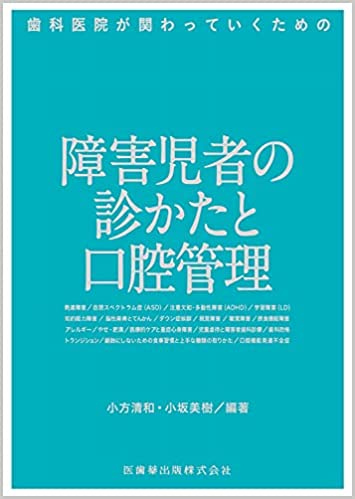 『歯科医院が関わっていくための障害児者の診かたと口腔管理』 『歯科医院が関わっていくための障害児者の診かたと口腔管理』
|













