|
1:発達障害または神経発達症群
(1)神経発達症群とは
神経発達症群とは生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさ・偏りと、その人が過ごす環境や周囲の人との
かかわりのミスマッチから、社会生活に困難が発生する脳機能障害です。
通常は低年齢から発症します。
(2)神経発達症群の分類
①神経発達症群の分類-1(DSM-5 2013)
Ⅱ-1 知的能力障害群 Ⅱ-2 コミュニケーション障害群 Ⅱ-3 自閉スペクトラム症
Ⅱ-4 限局性学習障害 Ⅱ-5 注意欠如・多動性障害 Ⅱ-6 運動障害
②神経発達症群の分類-2 (ICD-11 2018)
1.1 知的発達症 1.3 自閉スペクトラム症 1.4 発達性学習症 1.7 注意欠如多動症
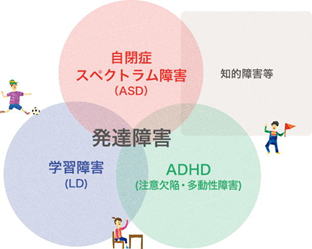
2:発達について
(1)発達とは
受精から死に至るまでの人の心身、及びその社会的な諸関係の量的及び質的変化・変容をいいます。
からだ・精神などが成長して、より完全な形態や機能をもつようになることです。
具体的には、身体の成長、運動機能、言語機能、コミュニケーション能力などの発展を言います。
参照:「発達年齢と発達過程」
(2)発達の評価
①運動発達の評価
姿勢の観察、姿勢反射の評価を行います。
②精神発達の評価
言語、微細運動、生活習慣行動の評価を行います。
③社会性の評価
対人関係の評価を行います。
3:発達検査について
(1)発達検査とは
心理検査の一種で、子どもの心身の発達の度合いを調べる検査です。
知的能力だけではなく、身体運動能力や社会性の発達なども含めて、発達水準を図るものです。
発達検査の検査結果から子どもの発達の度合いが示される.
発達プロフィール、発達年齢、発達指数、などの数値結果を知ることができる.
(2)発達プロフィール
折れ線グラフのように記され、発達の全般的な遅れや、発達障害の特徴を把握すること が可能です。
発達障害がある子どもの場合は、一定のプロフィールパターンが見られる傾向があることから、診断の参考に
使用されています。
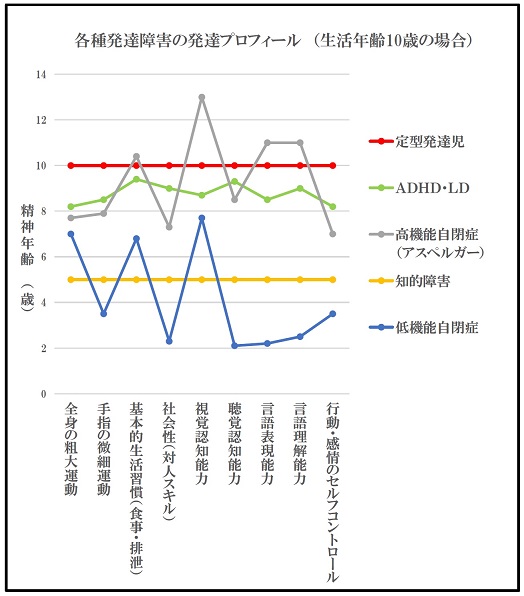
(3)発達年齢(DA:Developmental Age)
被験者の、精神年齢を示すものです。
(4)発達指数 (DQ=developmental quotient)
小児期の身体・精神機能の発達を評価する発達検査の結果として算出されます。
発達年齢(developmental age:DA)を暦年齢の比で示したものが発達指数です。
算出式:発達指数=DQ=DA÷age×100=発達年齢÷暦年齢×100
DQ=発達年齢/生活年齢×100
対象:発達課題が明確で、個体差の少ない乳幼児期に用いられます。
判定基準(新版K式の場合): 正常80~120、境界域70~79、遅滞69以下
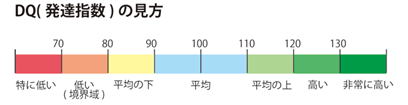
(5)発達年齢の指標
大まかな発達年齢の指標です。
2歳になると、2語文を話すようになります。
発達の早い子は「ブーブー,こっち,来た」などの3語文も話すようになります。
2歳半ぐらいになると、二語文・三語分を話せるようになります。
走る・ジャンプすることができるようになります。
手先がずいぶんと器用になり、ブロックなどの細かい作業ができるようになってきます。
3歳を過ぎると、一人で洗顔が出来、ボタンを留めることが出来れる様になります。
この時期から、簡単な歯科治療が可能とされています。
4歳ごろは周囲の人に興味関心を持ち、かかわりを持つようになります。
友だちとの遊びを通じて、社会性を身につけていく時期です。
ルールを決めて遊んだり競い合ったり、同じ行動を取ったり、相手に合わせながら遊ぶ行動が増えてきます。
ごっこ遊びも楽しめるようになってきます。
時にケンカになってしまうことも増えますが、その経験がとても大切と言えます。
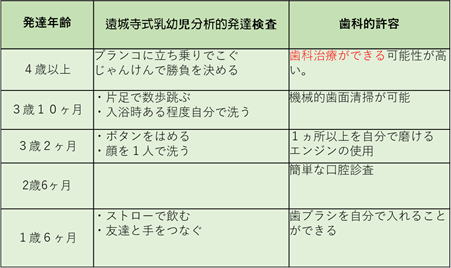 参照:「発達年齢と発達過程」 参照:「発達年齢と発達過程」
4:各種の発達検査
(1)改定日本版デンバー式発達スクリーニング検査 (JDDST-R)
①検査対象---6歳まで、です。
②検査時間---15-20分程度です。
(2)遠城寺式乳幼児精神発達診断検査
1958年、九州大学の遠城寺宗徳教授らによって発表された、日本で初めての乳幼児向けの発達検査法です。
①適応範囲---0か月~4歳7か月
②所要時間---30分程度(実地者によって前後あり)
③実地方法
観察者が保護者と子どもの関わりをチェックする.
特別な器具などがなく、簡単なテストを4、5か月の間隔で実施します。
検査内容は、運動、社会性、言語の3分野から質問されされます。
移動運動、手の運動、基本的習慣、対人関係、発語、言語理解の6つの領域で診断されます。
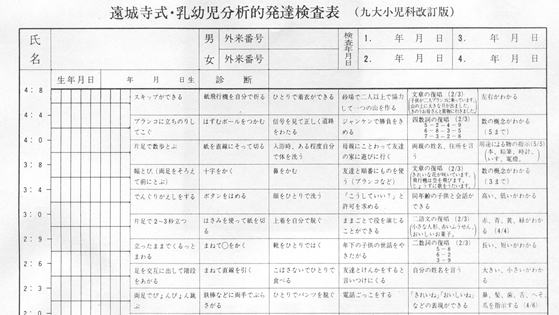
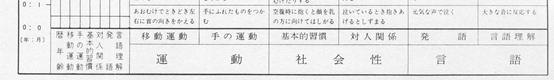
(3)津守・稲毛式乳幼児精神発達診断検査
①適応範囲---後1ヶ月から7歳まで
領域…0~3歳:運動、探索・操作、社会、食事・生活習慣を評価します。
領域…3~7歳:運動、探索、社会、生活習慣、言語を評価します。
②所要時間---約20分程度
③実地方法
母親など子どもの養育者に個別面接を行います。
運動、探索、社会、生活習慣、言語」の5領域の438の質問項目から構成されています。
5領域ごとに発達年齢が算出されます。
(4)新版K式発達検査
1983年、京都市児童院-現京都市児童福祉センターで開発され標準化された検査です。
2001年、新版K式発達検査2001が刊行されました。
①適用範囲:0歳~成人
②所要時間:30分~1時間程度
③実地方法
1対1で個室で実地。
おもに音がなるおもちゃやミニカーなど、乳幼児が興味があるもので検査します。
姿勢・運動、認知・適応、言語・社会→3領域を評価します。
子どもの自然な行動を観察できる点が特徴です。
あくまで自然な行動を観察して考察していくため、何度か行うこともあります。
|













