| �ېH�E������Q���Â̏����ƊԐڌP�� |
| |
�͂��߂� |
| |
����ɐېH������Q�Ƃ����Ă����̕a�Ԃ͐獷���ʂł��B
�S���o���ێ悪�o���Ȃ����A���Âɂ���Ă͉��P����\����������B
���P�̉\���͒Ⴍ�A���炩�̑㏞�I���@��I�Ȃ���Ȃ�Ȃ����B
�Ǐ�͌y�x�ŁA�����̌P����㏞�I���@�Ō�����H�ב����鎖���o������B
��Q�̒��x���ǂ��Ȃ̂������ɂ߁A����ɉ��������ÁE�P�����v�悷�邱�Ƃ��悸�͑����ƂȂ�܂��B
�F�X�ȌP�����@������܂����A�����ł͌ʂ̌P�����@�����b���A���ۂɂ͕a��ɍ��킹�Ă�����g�ݍ��킹�A���j���[��g�ݗ��Ă邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@���ÁE�P���̗���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f���E�]���E�v�� �@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����P�� �i�Ⴆ��A��b�g���j �@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԐڌP�� �i�Ⴆ��A�f�U��j �@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ĕ]��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڌP�� �i�Ⴆ��A�ΐ�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X�N�Ǘ�
|
| |
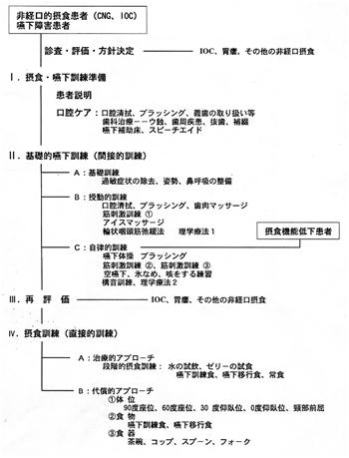
|
| |
�T�F�����P�� |
| |
���ۂ̐ېH�����P�����n�߂�O�ɁA������������I�ɍs�����߂ɁA���o���̐������s���܂��B
���o���̕ې��⎕�Ȏ��ÁA���o�����ǂɑ��鎡�ÂȂǂɓw�߂āA���ǂ����o�������܂��B
�i�P�j���o���|
�@�@�@���ӓ_
�@�@�@�@�@�@�P�@�����Ƃ��Ċ��҂���̉E������s�����ƁB
�@�@�@�@�@�@�Q�@�̈ʂ̊m�ہi���ʂ܂��͂R�O�x��ʁj�����A�O�����ێ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�R�@�K����������B
�@�@�@�@�@�@�S�@�ɂ��Ȃ����ƁB
�@�@�@�@�@�@�T�@���@�͉�����O���֍s���܂��B�@�i�c�Ԃ����ɑ��荞�܂Ȃ����߁j
�@�@�@�@�@�@ �E������@�@�@�@�@ �E������@�@�@�@�@ ������O�� ������O��
�i�Q�j�u���b�V���O�@�@
�@�@�@�@ ����i�v���[�N�j�̕t�����ʂ����ƁB
�@�@�@�@ ��{��{���������ƁB
�@ �@�@�@���ɂ͐��ߏo���t�p���ĉ���̗L�镔���������鎖���K�v�ł��B
�@�@�@ �@�⏕���̕��p�B�i���̌����ւ̗����ɒ��ӂ��A����E�뚋���N����Ȃ��悤�Ɂj
�i�R�j���o��� �@�@
�@�@�@�@���ӓ_
�@�@�@�@�@���t�̒������\���ۂ��̔�����s���Ă�����{���ĉ������B
�@�@�@�@�@�z���̐����B
�@�@�@�@�@���j�̗����ɒ��ӁB
�i�S�j�ܟ�
�@�@�@�@�@�\�Ȃ�ϋɓI�ɂ������͂��Ă��炢�܂��B
�@�@�@�@�@�ܚu�͂��Ȃ���ʓI�ȋ@�\�P���ƂȂ�܂��B
�i�T�j�`���̒����E��舵�����̐���
�@�@�@������Q�̕����`�����g�p����Ă��鎖�͒���������܂���B
�@�@�@�������́A�K���`���ɑ���m���������Ă����ĉ������B
�@�@�@�`��������O�Ɂc
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�悭�����������A���̒��ɐH�ׂ����������悤�ɂ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���ɉ��ꂪ�t�����Ă��Ȃ����m�F���A���łʂ炵�܂��B
�@�@�@�@�������`���̓�����E���O�����̃R�c
�@�@�@�@�@1)������F
�@�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ����i��{�̕�����ʓI�Ɉ��肵�₷�����߁j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N���X�v�̒��E�����͌����Ă��邽�߁A�܂��N���X�v���|���鎕�̈ʒu�܂Ŏ����Ă����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���S�̂��w�Ŏx���A���E�����ɉ����Čy���������A�������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ċ`�������œ���Ȃ����ƁB�N���X�v�̕ό`��A�j���̌����ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ȋ`���́A�������莝���Č뚋�̂Ȃ��悤�\�����ӂ��邱�ƁB
�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�l�����w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���A�e�w�����̏�ɒu���A�l�����w���� �������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A�e�w�̒܂��N���X�v�Ɋ|���l�����w�����̏�ɒu���A�e�w�������グ�܂��B
�@�@�@�A�S�����`���̓�����E���O�����̃R�c
�@�@�@�@�@�@�@1)������F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�����ɓ���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�̏ꍇ�́A�`���̒��������w�ʼn������z�������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�̏ꍇ�́A����̐l�����w�����E�̎��̏�ɒu���A�e�w���{�̉��ɓY���o���̎w��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��ނ悤�ɋ`�������肷��܂Ōy�������ɉ������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�Q�j���O�����F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���̒[�Ɏw�������Ă͂����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@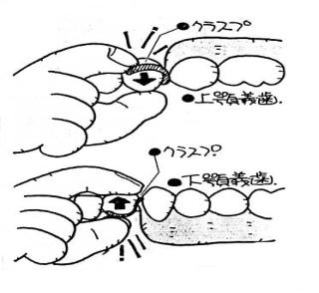
�@�@�@�B�`���̎����
�@�@�@�@�@�@�@�`���̉���́A�ۂ̑��B�ɂ���Ď����̉��ǁA�������̒����A���L�̌����ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�`���͖��H��ɂ͂����A���|���s���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@���ɗ[�H��E�A�Q�O�̐��|���d�_�I�ɍs���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�`���̕\�ʂɏ���t���Ȃ��悤�y���͂Ő��|���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�����܂͌����܂��܂ނ��̂�����A�`���������邱�Ƃ�����g�p�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@���ꎕ���܂̎g�p�͌��ʓI�ł����A�K���u���V�ł̐��|��Ɏg�p�̂��ƁB
�@�@�@�C�c�����̎����
�@�@�@�@�@�������̂�����́A�P�{�ł����������c���w�͂��̐S�ł��B
�@�@�@�@�@���ɁA���ꎕ�ɐڂ��Ă��鎕�͉��ꂪ�t�����₷���̂Œ��J�ɐ��|����K�v������܂��B
�@�@�@�D�`���̕ۊǕ��@
�@�@�@�@�@�`���̍ޗ��ł��郌�W���͋z������L���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@���O�����Ƃ������������Ȃ����Ƃ���ł��B
�@�@�@�@�@��������Ƌ`���ɘc�݂��A�K���������Ȃ�����A����錴���ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�`�����|��A�ۑ��p�e��ɐ������`����Z���Ă����܂��B
�@�@ �@�@�����Ƃ��Ė�Ԃ͋`�������O�����ƁB
�@�@�@�@�@�@�q�� �R�r
�@�@�@�@�@�@�@�@�ۂ̑��B�i�J���W�_�ۂȂǁj��h���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�`���͊�{�I�ɔS�����S�ł��邽�߁A���O�����ƂŔS���̌��s���͂���܂��B
�i�R�j���Ȏ���
�@�@�@�P�j�����̎����@�@�Q�j�����a�̎����@�@�R�j��Ԏ��Ái�����C���A�`���j
�i�S�j���̑��̎���
�@�@�@�P�j���o�����ǂ̑Ώ����@�@�@�Q�j�S�������̑Ώ����@
|
| |
�U�F�ԐڌP�� |
| |
�ԐڌP���Ƃ�
�@�ېH�E�����ɊW����튯�̉^�����⋦�����̉��P��}��ړI�ŁA���ۂɌo���ېH���n�߂�O�ɁA
�@�o���ێ�ɕK�v�ȋ@�\���������邱�Ƃł��B
�@�{���͌o���ێ悪�s�\�ȕ��Ɏ��{���܂����A�o���ېH���Ă�����̌��o�P�A�Ƃ��Ă����p�\�ł��B
�@�@�@�@�@�@�P�F��b�P��
�@�@�@�@�@�@�Q�F�����I�P��
�@�@�@�@�@�@�R�F�����I�P��
�P�F��b�P��
�@�@
�@�i�P�j�ߕq�Ǐ�̏����@
�@�@�@�@�ېH�E������Q��L����l�ɂ́A��ʁE���o�̈�ɗl�X�Ȓ��x�̉ߕq��L����������܂��B
�@�@�@�@�ߕq������ƁA�h���ɑ��Ċ��o�[�^���n���K�ɔ����o���Ȃ����߁A�@�\�̔������������j�Q����܂��B
�@�@�@�@����ɂ́A�ېH�P�����̂��̂��s�\�Ɉׂ邩������܂���B
�@�@�@�@�]���āA�ߕq�̂���Ǘ�ł́A���ׂĂ̐ېH�P���ɐ悾���ĒE������s�������K�v�ł��B
�@�@�@�@�ߕq�̑��ݕ��ʂ̊m�F
�@�@�@�@�@�@�ߕq���ۂ͐g�̂̒��S�ɋ߂����ʂقǔ����p�x�������A�Ǐ�������Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�]���āA���̊m�F�ɂ����S�����琳���Ɍ�������҂̎菶�ɂ���čs���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�聨�r�������z����ʁ����̎��́����o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@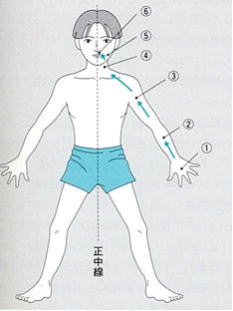 �@�������璆�S�������čs���܂��B �@�������璆�S�������čs���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�ł����p
�@�@�@�A�P�����@
�@�@�@�@�@�@�ア�h�����A�h�����ʂ��ړ��������ɗ^��������̂������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�畆�ʁF��҂̎菶�Ŕ畆�ʂ̉ߕq���ʂ��������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���o���F��w�ň������܂��B
�@�@�@�@�@�@�ł����ӂ��ׂ����Ƃ́A�E����̎��{���ɒ[�Ȋ��҂̕��S�Ɉׂ�Ȃ��l�ɐS�����鎖�ł��B
�@�@�@�@�@�@��ɂ������A�������ċ��ۂ̌����ƈׂ��Ă��܂����Ƃ�O���ɒu���K�v������܂��B
�@�i�Q�j�p��
�@�@�@�@��{�p���i�J�n�p���j�E�E�E�z���O���@����ݒu�A��ʂȂ�R�O�x���
�@�@�@�@�@�@���̎p���́A�S��،Q��S�g�̋ؓ��������b�N�X���Ě����̓������X���[�Y�ɂȂ�A
�@�@�@�@�@�@�뚋���N�����ɂ����낳��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@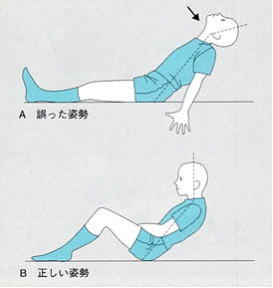
�@�@�@�@�@�@�@�@�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�ł����p
�@�@�@�@�@�P�j�R�O�x��ʂ̉�U�w�I���_�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�ǂƐH���̉�U�w�I�O��W����A��ʂ̕����C�ǂɓ���\�����Ⴂ�ƍl�����܂��B
�@�@�@�@�@�Q�j�R�O�x��ʂ̌��_
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�����I�ȐېH�̏ꍇ�ɂ́A�H�킪�g���ɂ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �H���̔F�m������ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�R�j�z���O���̗��_�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�ȉ��̗��R�ŁA����O��̕����悭�A�܂��A���W�̓������ǂ��Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�F�H��̒ʘH���L����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�F�A���W�J���L����A�H��ƔS���̐ڐG�@�ʐς��傫���ׂ�̂Ś������˂��N����Ղ��Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�F�A���q�_�̃��J�j�Y���ŋC���̕ی삪�s���܂��B
�@�@�@�@�@�S�j�X�O�x���ʂƂ̔�r�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �X�O�x���ʂ̏ꍇ�A���o�̐H��ێ��@�\�������]�������҂ł́A����Ĉ����ɐH���ꍞ���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��U�w�I�Ɍ뚋�̉\���������Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�X�O�x���ʂɂ����Ă͉����A�㎈�̈ʒu�ɂ����ӂ��K�v�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㎈�F���͂ɏ�Q���������悤�z�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�����Ƃ��āA�����n�ʂɕt�����肳����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����āA�ԐڌP���̊J�n�ɐ旧���A���̊�{�p�����ێ��ł��邩�ۂ��̔�����s���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p���ێ�������ȏꍇ�ɂ́AROM�̎{�s���ɂ���āA�p���ێ��̊m�������݂܂��B
�@�@�@�A��{�p������̔��W
�@�@�@�@�@�@��{�p���̊m��������ꂽ��A���X�ɑ̊����N�����A�U�O�x��ʁA�X�O�x���ʂւƔ��W�����܂��B
�@�i�R�j�@�ċz�̐���
�@�@�@�@�@�ċz�̏d�v��
�@�@�@�@�@�@����ȐېH�������ɂ́A���O�͕���ꂽ��Ԃŕ@�ċz���ׂ���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���O�@�\�����サ�Ă���ꍇ�ɂ́A�@�ċz����Q����뚋�̌����ƈׂ肤��댯��������܂��B
�@�@�@�A����
�@�@�@�@�@�@����Ɍ��O�Ɗ{�����Ԃɂ��āA���ꂵ���Ȃ�Ȃ����x�̕@�ċz�����b�ԏo���邩���v���B
�@�@�@�@�@�@�@�����̎g�p���D�܂������A���L���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�X�e�����X���̋��Ȃǂ����p�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z���ԁF30�|60�b��
�@�@�@�B�P�����@
�@�@�@�@�@�@���������̎���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A�ċz�펾��������Ύ��O�Ɏ��Â��K�v�ł��B
�@�@�@�@�@�@�P��
�@�@ �@�@�@�@�@�@ ����Ɍ��O�Ɗ{�����Ԃɂ��āA���ꂵ���Ȃ�Ȃ����x�̕@�ċz�𑱂������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������̎������Ԃ����Ȃ��Ƃ��P�T�Ԃ��炢�����āA�y�ɕ@�ċz���o����悤�ɂȂ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ԃ𐔕b�ԉ����܂��B
�@�i�S�j��s���ɑ���A�v���[�`�@�@
�@�@�@�@�����瓭����������@
�@�@�@�@�@�@�h�������������ɂ����āA�ԐړI�Ɏh����^���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@��P�F�啔���Ɉڂ�
�@�@�@�@�@�@�@��Q�F�i�[�X�X�e�[�V�����ɒu���ȂǁB
�@�@�@�A���ڊ����瓭����������@
�@�@�@�@�@�@�@���ڊ��Ҏ��g�ɁA��ҁE���Î҂��h����^���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@��P�F���Î҂̐�����
�@�@�@�@�@�@�@��Q�F�ӎ����x���ɉ�킹���P����Ƃ����Ă��炢�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@��R�F��h��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �Qcm���̗����̂̕X���P�O���x�i�C�����܂ɓ���A���̕X�܂��g���Č���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̖т̐����ۂ𒆐S�ɁA���E�E�㉺�ɃA�C�X�}�b�T�[�W���s���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ԃ�10-15�����x�Ƃ��A�����ɐ������A�P����Ƃ��s�킹�āA�]�̕�������}��悤�ɓ����܂��B
�Q�F�����I�P��
�@�@�@�����I�ɍs���Ȃ����ɑ��A��ҁE�p�҂����{���܂��B
�@�i�P�j���o���@�@�i�O�q�j�@�@
�@�@�@�P�Ȃ鐴�|�ł͂Ȃ��A�@�\�P���Ƃ��Č��o���@���s���܂��B
�@�@�@���ꂪ���o��ʂ��Ē����ւ̎h���ƂȂ�܂��B
�@�i�Q�j�u���b�V���O�i��j �i�O�q�j
�@�@�@�P�Ȃ鐴�|�ł͂Ȃ��A�@�\�P���Ƃ��ău���b�V���O���s���܂��B
�@�@�@��������o��ʂ��Ē����ւ̎h���ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�i�R�j�����}�b�T�[�W
�@�@�@�@�ړI
�@�@�@�@�@�@����҂̏ꍇ�ɂ́A�����}�b�T�|�W�͎����̌��s���悭���邽�߂ɍs���܂����A������Q���҂ł�
�@�@�@�@�@�@�ȉ��̌��ʂ����҂���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�j���o���̊��o�@�\�����߂�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�j���t�̕���𑣂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�j�����^����U������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�j�����˂��y��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�T�j�{�̃��Y�~�J���ȏ㉺�^����U������B
�@�@�@�A���@
�@�@�@�@�@�@���o�O����S���ɕ����A���̋�悲�Ƃɍs���܂��B
�@�@�@�@�@�@���O����ԂŎ��{����̂����z�B
�@�@�@�@�@�@�@�P�j�����Ƃ��đ�Q�w�̕��̕��������Ǝ����̋��ڂɒu���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�Q�j�O��������P�����Ɍ����Ă�����B
�@�@�@�@�@�@�@�R�j������̂͑O���牜�Ɍ������������Ŗ߂鎞�ɂ͂�����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�S�j�}�b�T�|�W�̗v�_�͎w�����₭�i�P�b�ԂɂQ�������x�j���Y�~�J���ɓ��������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@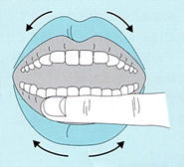
�@�@�@�@�@�@�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�ł����p
�@�i�S�j�؎h���P���|�@ �iVangede-�T�`�F�I�h���@�j�@�@
�@�@�@�@�K��
�@�@�@�@�@�@�ېH������Q���҂Ŏ����I�ɉ��L�̉^�����s���Ȃ�����ΏۂƂ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�ېH�����֘A���튯�̎h���A��������ړI�Ƃ����Z�ł��B
�@�@�@�A���
�@�@�@�@�@�@��w
�@�@�@�@�@�@�ꍇ�ɂ��ȋ��A ���u���V�ATooth Hetee�����g�p���܂��B
�@�@�@�B���@
�@�@�@�@�P�j���O�̃}�b�T�|�W
�@�@�@�@�@�@�P�F����O��E��Ń}�b�T�|�W����B �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���،Q���_�炩�����ĝ��݂ق����悤�ɐS�����܂��B
�@ �@�@�@�@�@�@�@ �����O�����l�Ƀ}�b�T�|�W���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@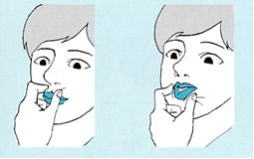
�@�@�@�@�@�@�Q�F��Q�w�����o�O��ɓ���ď���O��E�݁A�O���Ɍ������Ĉ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@ �����O�����l�Ƀ}�b�T�|�W���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@�R�F��Q�w������O�̐ԐO���ɒu���A�@�̕��Ɍ������ĉ����グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���l�ɂ��ĉ����O�ԐO�����I�g�K�C���Ɍ������ĉ��������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@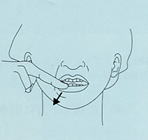
�@�@�@�@�@�@�S�F��Q�w������O�̏�ɉ������ɒu���A
�@�@�@�@�@�@�@�@��{�O�����ɑ��ĂĈ���������l�ɂ������Ə���O������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@���l�ɁA��Q�w�������O�̏�ɉ������ɒu���A���{�O�����ɑ��ĂĈ���������l�ɂ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@���O�����������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@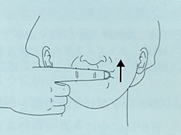
�@�@�@�@�@�@�T�F��Q�w�̎w�땔�Ŋ��҂̃I�g�K�C���̈���y���@���Ȃ���}�b�T�[�W���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�Q�j�j���̃}�b�T�|�W
�@�@�@�@�@�@�P�G�j������
�@�@�@�@�@�@�Q�G�j�S���̊g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Q�w�����p������j�S�����ɑ}�����A�j���O���ɖc��܂��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@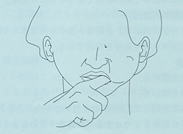
�@�@�@�@�R�j��̃}�b�T�|�W
�@�@�@�@�@A�F���O�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�I�g�K�C���̎w��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�g�K�C����[�����̂�������̕���������ɉ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ킿�A�I�g�K�C��A�I�g�K�C�������̃I�g�K�C �N�n���̂�������^��ɉ����グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@B�F�����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�F�f���^���~���[�A�X�v�[�� �����g�p���āA�܂��͑�Q�w��p���Đ�땔�����ꕔ�Ɍ������ĉ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�F�f���^���~���[�A�X�v�[�� �����g�p���āA�܂��͑�Q�w��p���Đ㉏�̑��Ɍ������ĉ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@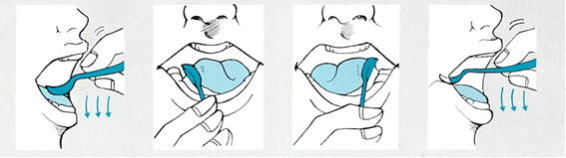
�@�@�@�@�S�j�̃}�b�T�|�W
�@�@�@�@�@�P�F�J���^��
�@�@�@�@�@�@�@�@���{�i���O�F�I�g�K�C���A�����F���{�O�����j�Ɏ�w�āA�J���^����U���B
�@�@�@�@�@�@�@�@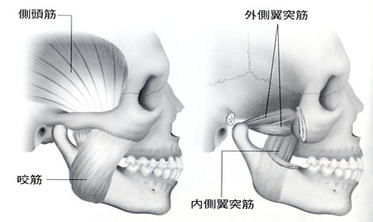
�@�@�@�@�T�j�㍜�㉺�،Q�̃}�b�T�[�W
�@�@�@�@��L���P�N�|���Ƃ��A�R�N�|���J��Ԃ��܂��B
�@�i�T�j����h���Ö@
�@�@�@�@�K��
�@�@�@�@�@�@�������ˑr���������͎㉻�������A�����̑��������i�畆�̃A�C�X�}�b�T�[�W�̏ꍇ�j�ΏۂƂȂ�܂��B
�@�@�@�A��p���J�j�Y��
�@�@�@�@�@�@���o�̉��x��36���ɕۂ���A���M���o�̓K���͈͂�29�[37���ŁA���͈͈̔ȊO�ł͗₽��
�@�@�@�@�@�@���邢�͔M���Ɗ����܂��B
�@�@�@�@�@�@���̊��o�̕ω��ɂ��A�ȉ��̋@���Ś������˂�臒l���ቺ���āA�H��̊��o���͂ɂ��
�@�@�@�@�@�@�������˂��U������₷���Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@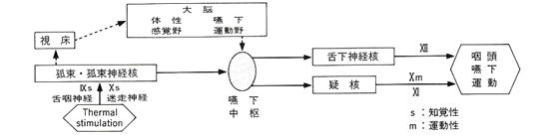
�@�@�@�B���
�@�@�@�@�P�j�����A�C�X�}�b�T�|�W
�@�@�@�@�@�@�P�FTooth Hette �A�Ȗ_�A�ȂǂɕX����Z���܂��B
�@�@�@�@�@�@�Q�F�X�|�C�h�ɐ������A����𓀂点�܂��B
�@�@�@�@�Q�j�畆�̃A�C�X�}�b�T�|�W
�@�@�@�@�@�@�P�F����h����i�`���R�[���h�A�}�C�R�[���h���j���g�p���܂��B
�@�@�@�C���@
�@�@�@�@�P�j�����A�C�X�}�b�T�|�W
�@ �@�@�@�@�P�F�h������
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�O���W�|�A����W�|�A�㍪���A�������
�@�@�@�@�@�Q�F���{���@
�@�@�@�@�@�@�@Logemann�̕��@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�̑O���W�|�ɗ�p�����h���q�e�T��A�������Ɍ����āi1 stroke������P�b�j���Ă܂��B
�@�@�@�@�@�@�@Logemann�̕ϖ@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���q�i�������Ȗ_ or Tooth Hette)�ɏ��ʂ̗␅�����āA����W��㍪�����y��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�`�R��h��������A�����ɋ������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���̗^�����Ƃ��ẮA�L�͈͂ɏ������h�����܂��B
�@�@�@�@�@�R�F���{����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ېH�P���J�n�O�G�Q�C�R���ԂĂ܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�ԁG���ƕ��p���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@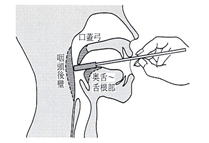 �@�@�@�@ �@�@�@�@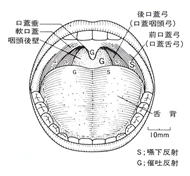 �@ �@
�@�@�@�@�Q�j�畆�̃A�C�X�}�b�T�|�W
�@�@�@�@�@�@�P�F�h������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʁi���A�j�A�����B�j�A�@�{�����i�{���B�j�W�|�A�㍪���A������ǁA�z���B
�@�@�@�@�@�@�Q�F���{���@
�@�@�@ �@�@�@�@�@����h����ɕX�����A���o���͂��̑��s�ɉ����āA�����h�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�R�F���{����
�@�@�@�@�@�@�@�@�ېH�P���J�n�O�G�Q�C�R���ԂĂ܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�H�ԁG���ƕ��p���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@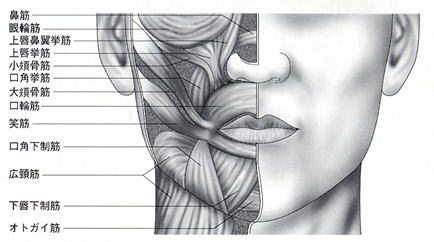
�@�i�U�j�֏�����ؒo�ɖ@�i�����f���]�|����Z�j
�@�@�@�@�@�@�����f���]�[����Z�Ƃ́A�A������̋����𑣂����@�ł��B
�@�@�@�@�@�@�֏�����̒o�ɂړI�ɂ͑��i���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�@�@�K��
�@�@�@�@�P�j�������ˑr���������͎㉻�������B
�@�@�@�@�Q�j�����Ԃ̐�H�ɂ��֏�������J���ɂ��� �Ȃ��Ă�����B
�@�@�@�A���@
�@�@�@�@�P�j�������˂�L���銳���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�b������w�ɂĔc�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɂ��b�������サ�����ɋ���ʂ�ێ����܂��B
�@�@�@�@�Q�j�������˂�L���Ȃ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�b������w�ɂĔc�����A����ʂɕێ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@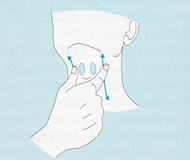
�@�i�V�j�o���[���P���@
�@�@�@�@�֏�������̒ʉߏ�Q�̃��n�r���e�[�V�����P���Ƃ��āA�N�����u�J�e�[�e����p�������@�B
�@�i�W�j���w�Ö@�[�P�i�̊��P���A�ċz�P���j
�@�@
�@�@�@�@�̊��P��
�@�@�@�@�P�j�z���E�̊��@�\���P�P��
�@�@�@�@�Q�j�߉���P��
�@�@�@�@�@�@�P�G�z���q�n�l�P��
�@�@�@�@�@�@�Q�G���s�q�n�l�P��
�@�@�@�@�R�j�ؗ͑����P��
�@�@�@�@�S�j�z���̃����N�Z�[�V����
�@�@�A�ċz�P��
�@�@ �P�j�I�ċz�P��
�@�@�@�@�@�@�P�G���s�q�n�l�P���i�]���P�]�@�j
�@�@�@�@�@�@�Q�G�ċz�p�^�[���̎w���i�����ċz
�@�@�B�̈ʃh���i�[�W
�@�@�@�@�P�j���Ñ̈ʁi�h���i�[�W�̈ʁj
�@�@�@�@�Q�j�C��������ړ��𑣂����߂̎�Z
�@�@�@�@�R�j�P�u��huffing�܂��͋C�Ǔ��z��
�R�F�����I�P��
�@�@�@�@�ӎv�̑a�ʂ��}��āA�w��������A�����I�ɓ�������ɑ��čs���P�����@�ł��B
�@�@�@�@
�@�i�P�j�����̑�
�@�@�@�@�ړI
�@�@�@�@�@�@�뚋�͐H���J�n�̈���ڂɋN����₷���A�����h�~����ړI�ōs���H�O�̏����̑��ł��B
�@�@�@�@�@�@�O��،Q�A��Ɋ֗^�����𒆐S�Ƃ����ؓ��������b�N�X�����܂��B
�@�@�@�A���{���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�����ċz�{�����ڂߌċz
�@�@�@�@�@�@�A �B �C�@�@�@�@ ���͋̃����N�[�[�V����
�@�@�@�@�@�@�D �E �F �G �@ �@�j�A��A���O�̉^��
�@�@�@�@�@�@�H �@�@�@�@�@�@�@�@�I���̐[�ċz
�@�@�@�@�@�@�@�@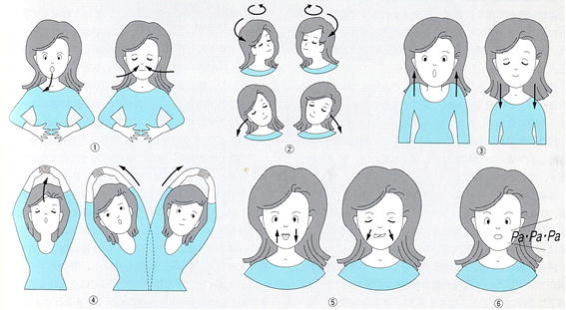
�@�i�Q�j�u���b�V���O�i�����I�ȃu���b�V���O�j
�@�@�@�@�����I�Ƀu���b�V���O���s�����Ƃ́A���o�ې��݂̂Ȃ炸�A���o���͏��؋y�ю�w���̑����I��
�@�@�@�@�������ɂȂ���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�i�R�j�؎h���P���[ �A �iVangede �T�a�F�\���I�h���@�E��R�@�j
�@�@�@�@�@�ېH������Q���҂Ŏ����I�ɉ��L�̉^�����s���銳�҂�ΏۂƂ��܂��B
�@�@�@�@�@�ېH�����֘A���튯�̎h���A��������ړI�Ƃ��܂��B
�@�@�`�F�����I�h���@
�@�@�@�@���O�̉^��
�@�@�@�@�@�P�j�����J����
�@�@�@�@�@�Q�j�������
�@�@�@�@�@�R�j���O�ˏo�@
�@�@�@�@�@�S�j���p����
�@�@�@�@�@�T�j�z�ĂP��
�@�@�@�@�@�@�@�@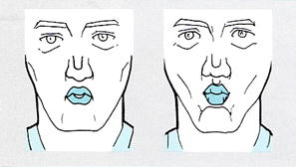 �@�@ �@�@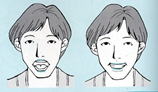 �@�@ �@�@
�@�@�@�A�j�̉^��
�@�@�@�@�@�P�j�j��c��܂���B
�@�@�@�@�@�Q�j�Ί�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�B��̉^��
�@�@�@�@�@�P�j����ׂ����đO���ɓ˂��o���B
�@�@�@�@�@�Q�j������E�̌��p���Ɏ����Ă���B
�@�@�@�@�@�R�j��ŏ㉺���O���Ȃ߂�B
�@�@�@�@�@�S�j��Ō��W���Ȃ߂�B
�@�@�@�@�@�@�@�@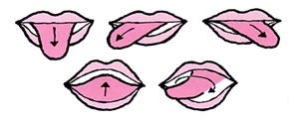
�@�@�@�@�@�⑫�FMasako�@�@�i�O��ێ������@(Tongue-Hold Swallow�F�ȉ�THS)
�@�@�@�@�@�@�@��̋ؗ̓g���[�j���O�̈�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�����������̚������������ƂȂ�㍪���ƈ�����ǂ̐ڐG�s�S�ɑ��A������Ǘ��N�傳����P���@�B
�@�@�@�@�@�@�@THS �͈����ǂ݂̂Ȃ炸�㍪���̌�މ^���傳����\������������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@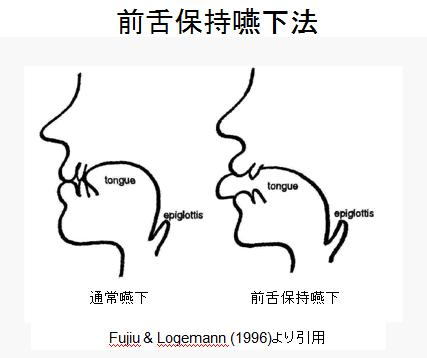
�@�@�@�C�J���̉^��
�@�@�@�@�@�P�j����傫���J����B
�@�@�@�@�@�Q�j�㉺��������������i����ʼn������A�Ǝw�����܂��j
�@�@�@�@�@�R�j���{�̑O���^���w���B
�@�@�@�@�@�S�j���{�̑����^���w���B
�@�@�@�D�����I�����P��----�b���A���A�̂��@��
�@�@�@�@�@�{���͎��R�ȏ�ԂŁA�b���ď��āA���ɂ͉̂��B���ꂪ��Ԃ��Ǝv���܂��B
�@�a�F��R�@
�@�@�@�@���O�̉^��
�@�@�@�@�@�P�j���O���̉^��
�@�@�@�@�@�@�@�@��Q�w������O�̓����ɓ���āA�O���Ɉ�������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂ɁA����O�ɗ͂����ē����ɒ��ߕt����悤�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���l�Ȃ��Ƃ������O�ɑ��Ă����{���܂��B
�@�@�@�@�@�Q�j���O�̏㉺�I�ȉ^��
�@�@�@�@�@�@�@�@��ԐO��ɑ�Q�w��u���āA�@�̕��Ɍ������ĉ����グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂ɁA����ɒ�R���ď�O������������l�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���l�Ȃ��Ƃ������O�ɑ��Ă����{���܂��B
�@�@�@�@�@�R�j�{�^���P��
�@�@�@�@�@�@�@�@�K���ȑ傫���̃{�^������v�Ȏ��łȂ��A�{�^�������O�����i���o�O�땔�j�ɕێ������Ď�����������A
�@�@�@�@�@�@�@�@��яo���Ȃ��悤�ɂ���ɒ�R�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�{�^���̑���ɃX�g���[�A�`���[�u�Ȃǂ��p���Ă����v�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@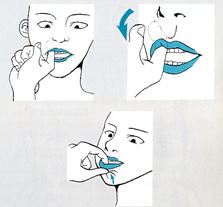 �@�@ �@�@
�@�@�@�A�j�̉^��
�@�@�@�@�@�P�j�j�̎��k�^��
�@�@�@�@�@�@�@�@�w���X�v�[����j�̓����ɑ}�����āA��������O���Ɉ�������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���҂���ɂ͖j�������߂��l�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�Q�j�j�̖c���^��
�@�@�@�@�@�@�@�@���������͎w��j�̏�ɒu�������Ɉ������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂���ɖj��c��܂���l�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@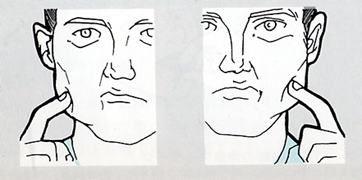
�@�@�@�B��̉^��
�@�@�@�@�@�P�j��̑O���^���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�X�v�[�������p���ɓ��Ă܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ċ��҂ɐ�땔�ʼn����o���悤�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���҂����̓�����s���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�X�v�[���Ő�땔�������ďグ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@����Ă�����A�X�v�[�����㉺���O�ɓ��āA������ʼn����Ԃ��l�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�Q�j��̑����^��
�@�@�@�@�@�@�@�@�X�v�[����㑤���ɉ����đ}�����Đ���������A���҂ɂ���������Ԃ��l�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@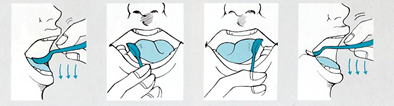
�@�i�S�j�؎h���P���[ �B �iVangede �U�F�����^���̂̎h���A�z���ABlowing�A�ܚu�j
�@�@�@�@�@�@�ړI�F �@���O���[�v�̋ؓ��@�\�̋����^�����h�����悤�Ƃ���P���B �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �z���E�����p�^�[�������P���A�Ђ��Ă͙E���ꔭ���p�^�[�����h�����鎖��ړI�Ƃ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�K���F �@�ېH������Q���҂̒��ł���r�I�@�\���ǂ��ǗႪ�ΏۂƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�z���P��
�@�@�@�@�@�P�j����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���،Q�y�ѐ���P�����A����ɂ���Ě����@�\�̉��P���ʂ����܂��B
�@�@�@�@�@�Q�j�g�p���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e��T�C�Y�̓����ȃv���X�`�b�N�X�g���[�A�����l�[�h�A�������g�p���܂��B
�@�@�@�@�@�R�j���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���҂���̂̐ېH����̓x�����ɉ����ă`���[�u�̑�����ς��Ă����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڂ̃`���[�u �� �זڂ̃`���[�u
�@�@�@�@�@�@�@�@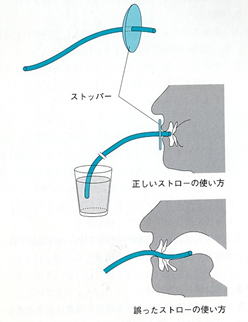
�@�@�@�A�����P���iBlowing�j
�@�@�@�@�@�P�j����
�@�@�@�@�@�@�@�@���o���͓��O�̋ؓ��ƌċz���P�����܂��B
�@�@�@�@�@�Q�j�g�p���
�@�@�@�@�@�@�@�@�J�A�X�C�A���D�Ȃ�
�@�@�@�@�@�R�j���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�F�@�ő����z�����݁A���Ő����o���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�F�X�C�̉𐁂������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�F�V���{���ʂ𐁂��B
�@�@�@�@�@ �@�@ �S�F�J�𐁂��B�@�Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�B��̌P��
�@�@�@�@�@�@�Â����̂̏��Ђ����X�v�[���̏�ɒu���A���҂���ɐ�̐�łȂߎ��悤�Ɏw�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�C�ܚu�P��
�@�@�@�@�@�P�j�ړI
�@�@�@�@�@�@�@�@���O�A�j�A��A����W�̋����I�ȋ@�\�P���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɍ��o�ې��ɂ��𗧂B
�@�@�@�@�@�Q�j�K��
�@�@�@�@�@�@�@�@�����I�Ɋܚu���\�Ȋ��҂�ΏۂƂ���B
�@�@�@�@�@�R�j���
�@�@�@�@�@�@�@�@���A�ܟ���
�@�@�@�@�@�S�j���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�ېH��A�������͌��߂�ꂽ���ԂɎ{�s�B
�@�@�@�@�@�@�@�@���O�A�j���g�����u�N�u�N�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@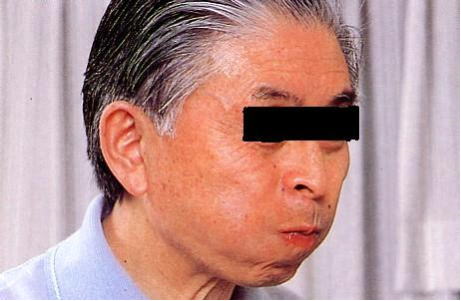
�@�i�T�j�ԐړI�����P���@�i���A�����̈ӎ����A�X�r�߁j
�@�@�@�@�����̈ӎ��� �iThink Swallow�j
�@�@�@�@�@�@���o���ɐH�����܂�ł���Ƃ��A�{���͖��ӎ����ɍs���隋�����ӎ����čs���܂��B �@�@
�@�@�@�@�@�@�������ӎ������A�W�����Ĉ��ݍ��ނ��Ƃɂ���āA�����̃^�C�~���O�����ꂽ�뚋�ɑ��Č��ʂ������܂��B
�@�@�@�A��
�@�@�@�@�@�@�H���Ȃ��ɚ���������s�����Ƃł��B
�@�@�@�@�@�@�������s�����Ƃ��u�������v�Ƃ����܂��B
�@�@�@�@�@�@����ɂ���āA�����Ɏc�����Ă���H�����N���A�ł��܂��B
�@�@�@�B�P�����P��
�@�@�@�@�@�@�P�����A�P�́A�A���N���A�������͌뚋�����H����r�����邽�߂ɗL���ł��B
�@�@�@�@�@�@�ېH���ɊP�����E�P�����A����ɋ����s���܂��B
�@�@�@�@�@�@����ɂ��A�뚋�����炵�A�x���̗\�h�ɖ𗧂��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�C�����炦�����iPseudo-Supraglottic Swallow�j
�@�@�@�@�@�@�H��������O�ɑ����z���āA�ꎞ�I�ɑ����~�߂܂��B
�@�@�@�@�@�@����Ś������s���A����ɑ���f���o���܂��B
�@�@�@�@�@�@����ɂ�萺�嚋�������㏸���A�뚋���N����ɂ����Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�����ɁA�C�ǂɐN�������H���\�o���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�i�V�j���w�Ö@�[�Q�i�̊��P���A�ċz�P���j
�@�@�@�@��������P���i�V���L�A�E�G�N�T�T�C�Y �j�@�ishaker�@exercise�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ړI�F�A���̑O����^�������P���āA�I�ɂ̂ǂ��J���₷������B �@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㍜����ʂ̌���𑣂��܂��B�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�F���ɋ����ɐQ�遨���̎w�悪��������x�ɓ���������i����������Ȃ��悤�Ɂj�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F1�A2��1��3��s���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@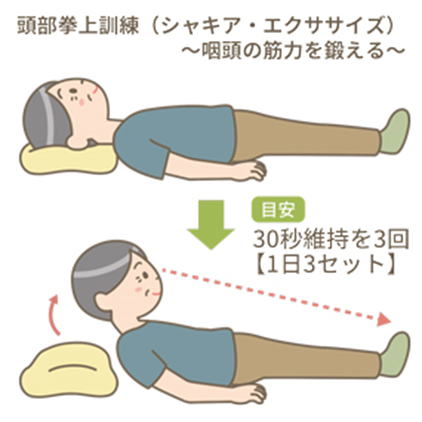
�@�@�@�A�v�b�V���O�E�v�����O�P���iPushing exercise�j/�iPulling exercise�j
�@�@�@�@�@�@�������莝���グ����Ƃ������㎈�ɗ͂�����^���ł��B
�@�@�@�@�@�@���˓I�ɑ����炦���N���邱�Ƃ𗘗p���āA����W �̋���A���т̓��](�������)���������Č뚋��h�~
�@�@�@�@�@�@���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����P���ł� �B
�@��L�̏����P���A�ԐڌP�������{������A���̌��ʂ��ĕ]�����ĉ������B
�@���̌��ʁA�@�\�̉��P���F�߂�ꂽ��A���ۂɐH�����g�������ڌP���ւƐi�߂܂��B
�@�ڍׂ́A�u�ĕ]���v�A�u���ڌP���v��
|
| |
�Q�l���� |
| |
�w�ېH������Q�w ��2�� (�W�����꒮�o��Q�w) �x�@���c ���A �Ŗ� �p�M�@��w���@�@2021
�w������Q�|�P�b�g�}�j���A�� ��4�Łx�@���ꚋ���`�[���A���� ��Y�@�㎕��o�Ł@2018
�w�ېH�����r�W���A�����n�r���e�[�V�����x�@��엘���@�w�����f�B�J���G���� �@2017
�w������Q�̂��Ƃ��悭�킩��{�x �@������Y�@�u�k�Ё@2014
�w������Q�i�[�V���O�\�t�B�W�J���A�Z�X�����g���皋���P���ցx�@���q ��悢�A���{ �ێu ���A��w���@�@2000
�w���ナ�n�r���e�[�V������w�x�@��쒼��@�P�X�X�X�@�����o�Ł@
�w������Q�̗Տ��F���n�r���e�[�V�����̍l�����Ǝ��ہ@���{������Q�Տ�������@�㎕��o�Ł@1998
�w�x�b�h�T�C�h�̐_�o�̐f�����x�@�c�� �`�� �@��R��
�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@�@���q�F�m�@��쒼��@�㎕��o�Ł@�P�X�X�W
�w������H�ׂ�\������QQ&A�x�@���� ��Y�@�@�����@�K�o��
�w�ېH�E�������n�r���e�[�V�����x�@�˓��h��
�w�Տ��_�o���Ȋw�@��R�Łx�@���R�@�����@��R��
�w�V�Տ����Ȋw�@��U�Łx�@���v�j���@�@���`�x�Y�@��w���@
�w�b�k�h�m�h�b�`�k�@REHABILITATION�ʍ��@�����]�@�\��Q�̃��n�r���e�[�V�����x�@�]�����v�ق��@�㎕��o�Ł@�P�X�X�T
�u�P���@�̂܂Ƃ߁i2014 �Łj�v�@���ېH�������n��@18�i1�j�F55?89, 2014
�uIndex of dysphagia: A tool for identifying deglutition problems�v �@Susan M. Fleming�@Dysphagia1987, Volume 1, Issue 4, pp 206-208 |

 �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@
 �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@