 |
������S�@�i�����̋@�\�ƕa�C�ƌ��o�P�A�j |
 |
mail�Finfo@aofc-ydc.com
|
�s���Ⴊ���ɂ���-�e�_
|
 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
|
|
| �s���ǁiAnxiety-disorder�j |
�͂��߂ɁF�s���ǂ̕���
�@A�F�s���ǁi�s���_�o�ǁj
�@�@�@�@
�@�@�@�@�P�F�����s����(�����s����Q) �@�@�@�@
�@�@�@�@�Q�F�I���g��(�������)(SM:Selective Mutism) �@�@�@�@
�@�@�@�@�R�F���ǐ����|�ǁ@(specific phobia) �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�P-�������|�ǁ@�@�Q-�������|�ǁ@�@�R-�����|�ǂ܂��͗����|�� �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�S-�����|�ǁ@�@�T-��[���|�ǁ@�@�U-���ȋ��|�� �@�@�@�@
�@�@�@�@�S�F�Ќ�s���� �@�@�@�@
�@�@�@�@�T�F�p�j�b�N��
�@B�F�����ǁi��������Q) �@�@
�@�@�@�@�P�F������ �@�@�@�@
�@�@�@�@�Q�F�X�`���|�ǁi�g�̏X�`��Q)
�P�F�����s���ǁ^�����s����Q
�i�P�j�T�O �@
�@�@�@�@�����Ώہi�ʏ�͕�e�j����̕����ɑ��Ĕ��B�i�K�ɕs�����Ŏ����I������ȋ��|���o�����Ԃł��B�@
�@�@�@�@�����͂��̂悤�ȕ�����K���ɂȂ��ĉ�����悤�Ƃ��܂��B
�@�@�@�@���������������ꍇ�C�����͔ߒɂȂ܂łɍĉ�邱�Ƃ݂̂Ɏ���ꑱ���܂��B
�@�@�@�@����8�`24�J���̏����ł͐���Ȋ���ł���ƌ����܂��B �@
�@�@�@�@�Ώۂ̉i�����Ƃ������o�����B���C�e�͂�����߂��Ă���Ƃ������Ƃ𗝉�����悤�ɂȂ�Ώ�������̂��ʏ�ł��B
�@�@�@�@
�i�Q�j�a���E�U�� �@
�@�@�@�@������̃X�g���X�������s���ǂ�U�����邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@��F�ߐe�ҁC�F�l�C�܂��̓y�b�g�̎��B�]���A�]�Z�A�ȂǁB
�i�R�j�Ǐ� �@
�@�@�@�@�����͂����ΐg�̓I�D�i�𗈂��܂�
�@�@�@�@�@�@��F���ɁA�ݒɂȂǁB
�@�@�@�@�����s���ǂ������Γo�Z�i�܂��͓o���j���ۂ̌`�Ō���ė��܂��B
(4)�f�f �@�@
�@�@�@�@�����s���ǂ̐f�f�́A�a��ƕ�����ʂ̊ώ@�ɂ���čs���܂��B. �@�@
�@�@�@�@�Ǐ�ƒ����4�T�Ԉȏ�݂��A�L�ӂȋ�ɂ܂��͋@�\��Q�𗈂��Ă��܂��B �@�@�@
�@�@�@�@�@�@��F�N����̎Љ�I�����܂��͊w�Z�̊����ɎQ���ł��Ȃ��B
�i�T�j���� �@�@
�@�@�s���Ö@ �@�@�@
�@�@�@�@����I�ȕ������n���I�ɋ�������s���Ö@�ɂ��. �@�@
�@�A�Ö@
�@�@�@�@�܂�ɍR�s���g���܂��B
�@�@�@�@�ɒ[�ȏǗ�ł́C�R�s����iSSRI�Ȃǁj���L�v�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�i�U�j�\��
�@�@
�@�@�@�@�@���Â��������������ł��C�x����w�Z�̒��f�̌�ł͍Ĕ����₷���Ȃ�܂��B �@�@
�@�@�@�@�@�e�Ƃ̕ʗ��ɑ��銵����ێ����邽�߂ɁC���̂悤�Ȋ��Ԃɂ͒���I�ɕ������v�悷��悤�����ΐe��
�@�@�@�@�@�w�����܂��B
�Q�F�I���g�فi��������j(SM�FSelective Mutism)
�i�P�j�T�O �@�@
�@�@�@�@�ƒ�Ȃǂł͘b�����Ƃ��o����̂ɁA�Љ�s���i�Љ�I�ɂ�����s���j�̂��߂ɁA�������̏�ʁE�ł�
�@�@�@�@�b�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Q�ł��B �@
�@�@�@�@
�i�Q�j�u�w
�@�@���ǔN�� �@�@�@
�@�@�@�@��ʓI�ɁA2�`5�̊Ԃɔ��ǂ��܂��B
�@�@
�@�A���Ǘ� �@�@�@
�@�@�@�@��������1000�l��7�l�ʂƂ���Ă��܂��B �@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@(2002�FThe Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) �@
�i�R�j�Ǐ�
�@�@�@�@�������̏�ʁE�ł����b���Ȃ��Ȃ��Ă��܂���Q�ł��B�@
�@�@�@�@�]�@�\���̂��̂ɖ�肪����킯�ł͂Ȃ��A�s���ʂ�w�K�ʂȂǂł����������܂���B�@
�@�@�@�@�P�Ȃ�l���m���p���������艮�Ƃ̈Ⴂ�́A�Ǐ�ϋ����A���R�ɂ͏Ǐ��P���Ȃ��_�ł��B
(4)�f�f�@ �@�@
�@�@�f�f�
�@�@�@�@���̏ł͘b�����Ƃ��ł���ɂ�������炸�A�������̏ł́A��т��Ęb�����Ƃ��ł��Ȃ������ł��B �@�@
�@�@�@�@���̎����ɂ���āA�w�Ə�A�E�Ə�̐��сA�܂��͎Љ�I�Ȍ𗬂̋@��������Ƃ����j�Q����܂��B �@�@
�@�@�@�@���̂悤�ȏ�Ԃ��A���Ȃ��Ƃ��ꃖ���ȏ㑱���Ă��鎖���f�f��ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@����́A�w�Z�ł̍ŏ��̈ꃖ���ԂɌ��肳��܂���B �@�@
�@�@�@�@�b�����Ƃ��ł��Ȃ��̂́A�b�����t��m��Ȃ�������A���܂��b���Ȃ��A�Ƃ������R����ł͂���܂���B �@�@
�@�@�@�@�R�~���j�P�[�V������Q�i��F�h���ǁj�ł͐��������܂���B�@
�@�@�@�@�܂��A�L�Đ����B��Q�A���������ǂ܂��͂��̑��̐��_�a����Q�̌o�ߒ��o�ߒ��ɂ̂N������̂ł�
�@�@�@�@����܂���B
(5)����
�@�@
�@�@�����̋���
�@�@�@�@�I���g�ق������N�������R�́A�l���ꂼ��ł��B
�@�@�@�@���̌��������ɂ߂邱�Ƃ����Â̈���ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
�@�@�@�@���Õ��@���l���ꂼ��ł��B
�@�@�@�@��Ԃ́A�J�E���Z���[�Ȃǂ̐��Ƃւ̑��k���厖�ł��B
�@�@�@�@�������q�̏ꍇ�́A�V��₨���������đ��l�Ə����Â������k�߂Ă����Ȃǂ̑Ή����@������܂��B
�@�A�i�K�I�\�I�Ö@�i�n���I�E����@�j
�@�@�@�@�����̎h���ɂ���ĕs�����������ꍇ�A���̎h����������邱�Ƃɂ���Ă������ĕs����������������A����������
�@�@�@�@���邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�@�@�s���̔����v���͎h���ł����A�������∫���̗v���͉���Ȃ̂ł��B
�@�@�@�@���̂悤�ȏꍇ�ɂ͉���𒆎~���邱�ƁA���Ȃ킿�h���Ɏ��R�ɐG��邱�Ƃ��L���ł��B
�R�F���ǐ����|�ǁ@(specific phobia)
�i�P�j�T�O �@�@
�@�@�@�@����̏A���A�܂��͑Ώۂɑ��鎝���I�ŕs�����ȋ������|�i���|�ǁj���炨����܂��B �@�@
�@�@�@�@���̋��|�ɂ��s������щ�����U������܂��B �@�@�@�@
�@�@��F �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�P�G�������|�ǁA�@�Q�G�������|�ǁA�@�R�G�����|�ǂ܂��͗����|�� �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�S�G�����|�ǁA�@�T�G��[���|�ǁA�@�U�G���ȋ��|��
�@�@�@�@ �@�@ �@�@
�@�@��O�F
�@�@�@�@�P�G�X�`���|�ǁA���a���|�ǂ��܂܂Ȃ��B
�i�Q�j�Ǐ� �@�@
�@�@�@�@���t�A�j�A�܂��͊O���ɑ��鋰�|�ǂ�L����l�́A���ۂɎ��_���邱�Ƃ�����܂��B �@�@
�@�@�@�@����͉ߓx�̌��ǖ����_�o���˂������ƋN�����ጌ���������N�������߂ł��B�@
�i�R�j�f�f �@
�@�@�f�f�
�@�@�@�@���҂́A����̏܂��͑Ώۂɑ��āA�����Ŏ�������i6�J���ȏ�j���|�܂��͕s�����F�߂��܂��B �@
�@�@�@�@���A�ȉ��̑S�ĂɊY�����܂��B �@
�@�@�@�@1)���̏܂��͑Ώۂ́A�قƂ�Ǐ�ɁA�����ɋ��|�܂��͕s���������N�����B �@�@
�@�@�@�@2)���҂����̏܂��͑Ώۂ�ϋɓI�ɉ�����Ă���B �@�@
�@�@�@�@3)���|�܂��͕s�������ۂ̊댯�Ɓi�Љ���I�Ȕw�i���l�����Ă��j�ނ荇��Ȃ��B �@�@
�@�@�@�@4)���|�C�s���C�����/�܂��͉�����C��������ɂ������N�����Ă��邩�C�܂��͎Љ�I�������͐E�ƓI�@�\��
�@�@�@�@�@���������Ȃ��Ă���.
�@
�i�S�j���� �@�@
�@�@���I�Ö@�i�n���I�E����@�j �@�@
�@�A�Ö@
�@�@�@�@�Ƃ��Ƀx���]�W�A�[�s���n��܁A�܂��̓��Ւf��̌���I�g�p���Ȃ���܂��B
�S�F�Ќ�s����
�i�P�j�T�O �@
�@�@�@�@���������{�������̑ΐl��ʂɔ��I����邱�ƂɊւ��鋰�|����ѕs���������܂��B �@
�@�@�@�@�����͉̏������邩�C�ς���̂ɋ����s�����܂��B.
�i�Q�j�u�w �@
�@�@���U�L�a��
�@�@�@�@13���ȏ�ł���\���������Ƃ������Ă��܂��B �@
�@�A����
�@�@�@�@�j���́A���������Ќ�s���̍ŏd�nj^�ł����𐫃p�[�\�i���e�B��Q��L����\���������Ƃ���Ă��܂��B
�i�R�j�Ǐ� �@�@
�@�@�@�@�����^�����ɂȂ艽���������Ȃ��B �@�@
�@�@�@�@�����k����A�����o�Ȃ��A�葫�̐k���B
�@�@�@�@�߂܂��A�����A���������A�Ԗʂ���A�����o��A�f���C������A�݂̂ނ������B�@�@
�@�@�@�@�ʏ�A����������1�l�ōs�����ꍇ�ɂ͕s���͐����܂���B
�i�S�j�f�f �@�@
�@�@�f�f�
�@�@�@�@���҂�1�ȏ�̑ΐl��ʂɊւ���A������(6�J���ȏ�)�������鋰�|�܂��͕s����L����K�v������܂��B �@�@
�@�@�@�@���|�ɂ́A���҂ɂ��ے�I�]�����ւ���Ă���K�v������܂��B �@�@
�@�@�@�@�@��---���҂����J��������A�p�������A�������͋��ۂ����A�܂��͑��҂̋C�����Q����A�ȂǁB �@�@
�@�@�@�@����ɁA�ȉ��̑S�Ă��F�߂���K�v������܂��B �@�@�@�@
�@�@�@�@1)�����ΐl��ʂ́A�قƂ�Ǐ�ɋ��|�܂��͕s���������N�����B �@�@�@�@
�@�@�@�@2)���҂����̏�ϋɓI�ɉ�����Ă���B �@�@�@�@
�@�@�@�@3)���|�܂��͕s�������ۂ̋��ЂƁi�Љ���I�Ȕw�i���l�����Ă��j�ނ荇��Ȃ��B �@�@�@�@
�@�@�@�@4)���|�A�s���A�����/�܂��͉�����A��������ɂ������N�����Ă��邩�A�܂��͎Љ�I�������͐E�ƓI�@�\��
�@�@�@�@�@ ���������Ȃ��Ă���B
�@
�i�T�j���� �@�@
�@�@�s���Ö@
�@�@�@�@�F�m�s���Ö@ �@�@
�@�A�Ö@
�@�@�@�@�Ƃ���SSRI�i�R����j���g�p����܂��B
�T�F�p�j�b�N��
�i�P�j�T�O �@
�@�@�p�j�b�N���� �@�@
�@�@�@�@�g�̏Ǐ�and/or�F�m�I�Ǐ�������s�����A�s���܂��͋��|���A�ˑR�ɌʂɒZ���Ԕ������錻�ۂł��B�@
�@�A�p�j�b�N��
�@�@
�@�@�@�@�p�j�b�N���삪�J��Ԃ��������A�T�^�I�ɂ͂���ɕt�����āC�����̔���ɑ��鋰�|�C�܂��͔�����N�����₷��
�@�@�@�@�ƍl�������������悤�Ƃ���s���̕ω��������܂��B �@�@
�@�@�@�@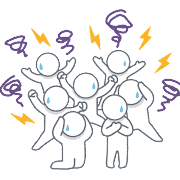
�i�Q�j�u�w �@�@
�@�@�D������
�@�@�@�@�p�j�b�N�ǂ͐N������܂��͐��l�������Ɏn�܂�܂��B �@�@
�@�A����
�@�@�@�@�j���F�������P�F�Q �@�����ɑ����Ƃ���Ă��܂��B
(3)�p�j�b�N����̏Ǐ� �@
�@�@�F�m�I�Ǐ� �@�@�@
�@�@�@�@���̋��|�B�@�@�@
�@�@�@�@���C�⎩���S���������Ƃւ̋��|�B�@�@�@
�@�@�@�@�����C��a���i�����������j�C�܂��͎������g���痣�E�������o�i���l���j�D �@
�@�A�g�̏Ǐ� �@�@�@
�@�@�@�@���ɂ܂��͋����s���� �@�@�@
�@�@�@�@�߂܂��A�s���芴�C�܂��͂ӂ�� �@�@�@
�@�@�@�@������ �@�@�@
�@�@�@�@�g���܂��͈��� �@�@�@
�@�@�@�@���S�܂��͕����s���� �@�@�@
�@�@�@�@���т�܂��̓`�N�`�N�� �@�@�@
�@�@�@�@�����܂��͐S�������� �@�@�@
�@�@�@�@���ꊴ�܂��͑��ꂵ�� �@�@�@
�@�@�@�@���� �@�@�@
�@�@�@�@�U��܂��͐k��
(4)�p�j�b�N�ǂ̏Ǐ�
�@�@
�@�@�@�@�p�j�b�N���삩��n�܂�܂��B�@
�@�@�@�@������J��Ԃ������ɁA����̂Ȃ��Ƃ��ɗ\���s����L�ꋰ�|�Ƃ������Ǐ����悤�ɂȂ�܂��B �@�@
�@�@�@�@����������Ƃ��Ǐ���悤�ɂȂ邱�Ƃ������Ȃ�܂��B
�i�T�j�f�f �@�@
�@�@�f�f�
�@�@�@�@�p�j�b�N��������Ă���(�p�x�̋K��͂Ȃ�)�A���̂���1��ȏ�̔����ɁA�ȉ��̕Е��܂��͗�����
�@�@�@�@1�J���ȏ㑱���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�@�@�@����Ȃ�p�j�b�N������N�������ƂɊւ��鎝���I�ȐS�z�A�܂��͂��̌��ʂɊւ���S�z������܂��B �@�@�@
�@�@�@�@�@�@��---�����S�������C���C������
�@ �@�@�p�j�b�N����ɑ���s�K���ȍs���I���� �@�@�@
�@�@�@�@�@�@��---����Ȃ锭���h�����Ƃ��ĉ^����ΐl��ʂȂǂ̈�ʓI�����������
�i�U�j���� �@�@
�@�@�Ö@�@�@�@
�@�@�@�@�����R����C�x���]�W�A�[�s���n��܁C�܂��͂��̗���. �@�@
�@�A�s���Ö@
�@�@�@�@�����ΖȊO�̑������܂��B
�@�@�@�@�@�@��---���I�Ö@�C�F�m�s���Ö@
|
| �Q�l���� |
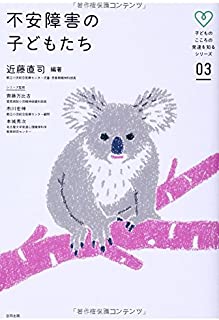 �@�w�s����Q�̎q�ǂ����� (�q�ǂ��̂�����̔��B��m��V���[�Y)�x �@�w�s����Q�̎q�ǂ����� (�q�ǂ��̂�����̔��B��m��V���[�Y)�x
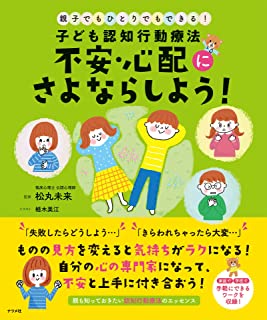 �@�w�q�ǂ��F�m�s���Ö@�@�s���E�S�z�ɂ���Ȃ炵�悤�x �@�w�q�ǂ��F�m�s���Ö@�@�s���E�S�z�ɂ���Ȃ炵�悤�x
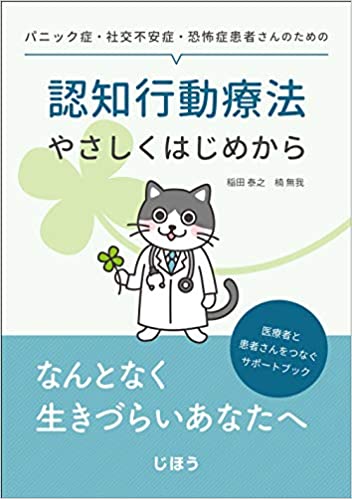 �@�w�p�j�b�N�ǁE�Ќ�s���ǁE���|�NJ��҂���̂��߂� �F�m�s���Ö@�₳�����͂��߂����x �@�w�p�j�b�N�ǁE�Ќ�s���ǁE���|�NJ��҂���̂��߂� �F�m�s���Ö@�₳�����͂��߂����x
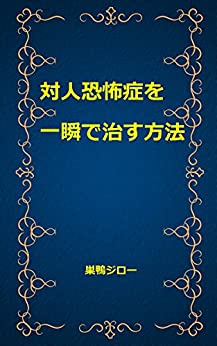 �@�w�ΐl���|�ǂ���u�Ŏ������@�x �@�w�ΐl���|�ǂ���u�Ŏ������@�x
 �@�w����҂����ȕ����~��20�̃A�h�o�C�X: ���ȋ��|�ǂł�����҂ɍs����I�x �@�w����҂����ȕ����~��20�̃A�h�o�C�X: ���ȋ��|�ǂł�����҂ɍs����I�x
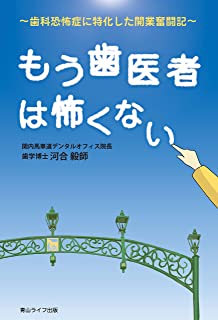 �@�w��������҂͕|���Ȃ�: �`���ȋ��|�ǂɓ��������J�ƕ����L�`�x �@�w��������҂͕|���Ȃ�: �`���ȋ��|�ǂɓ��������J�ƕ����L�`�x
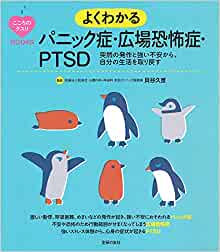 �@�w������̃N�X��BOOKS �悭�킩��p�j�b�N�ǁE�L�ꋰ�|�ǁEPTSD�x �@�w������̃N�X��BOOKS �悭�킩��p�j�b�N�ǁE�L�ꋰ�|�ǁEPTSD�x
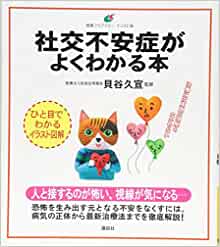 �@�w�Ќ�s���ǂ��悭�킩��{ (���N���C�u�����[�C���X�g��)�x �@�w�Ќ�s���ǂ��悭�킩��{ (���N���C�u�����[�C���X�g��)�x
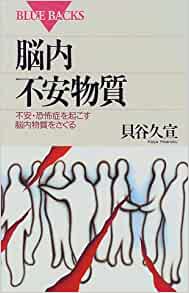 �@�w�]���s�������\�s���E���|�ǂ��N�����]�������������� (�u���[�o�b�N�X) �x �@�w�]���s�������\�s���E���|�ǂ��N�����]�������������� (�u���[�o�b�N�X) �x
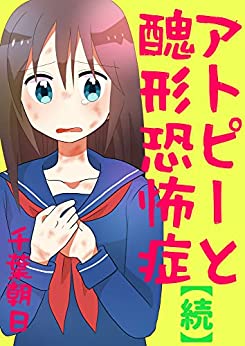 �@�w�A�g�s�[�ƏX�`���|�ǁy���z�x �@�w�A�g�s�[�ƏX�`���|�ǁy���z�x
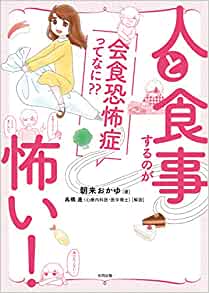 �@�w�l�ƐH������̂��|��!: ��H���|�ǂ��ĂȂ�??�x �@�w�l�ƐH������̂��|��!: ��H���|�ǂ��ĂȂ�??�x
 �@�w���_�Ȃ̖�-�R���_�a��E�R����E������E�R�F�m�ǖ�c-�͂⒲�׃m�[�g�x �@�w���_�Ȃ̖�-�R���_�a��E�R����E������E�R�F�m�ǖ�c-�͂⒲�׃m�[�g�x
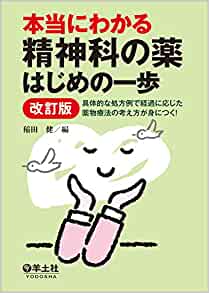 �@�w�{���ɂ킩�鐸�_�Ȃ̖�͂��߂̈���������x �@�w�{���ɂ킩�鐸�_�Ȃ̖�͂��߂̈���������x
 �@�w������̎��Ö�n���h�u�b�N ��13�� �x �@�w������̎��Ö�n���h�u�b�N ��13�� �x
|
|

�@
|
copyrightc 2021 YDC all rights reserved
mail�Fmail�Finfo@aofc-ydc.com
|
22-7-28
|


 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@

 �@�@
�@�@
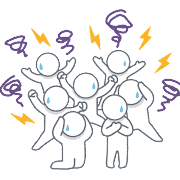
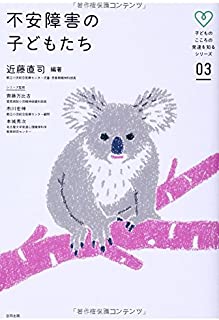 �@�w
�@�w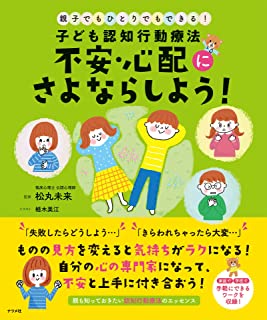 �@�w
�@�w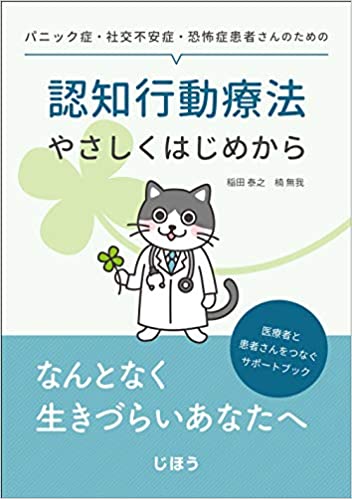 �@�w
�@�w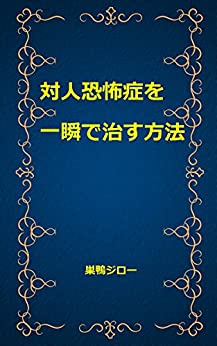 �@�w
�@�w �@�w
�@�w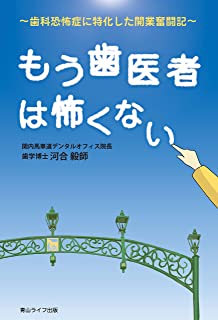 �@�w
�@�w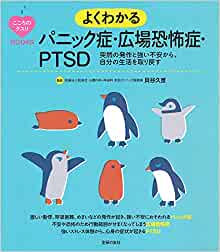 �@�w
�@�w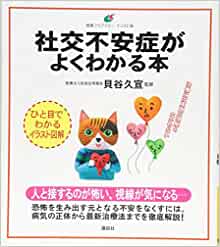 �@�w
�@�w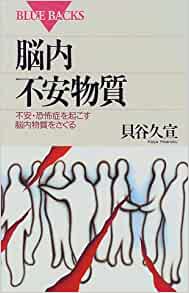 �@�w
�@�w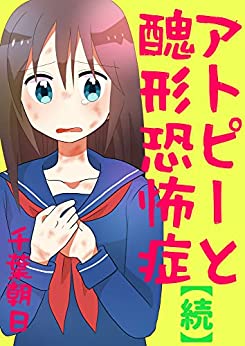 �@�w
�@�w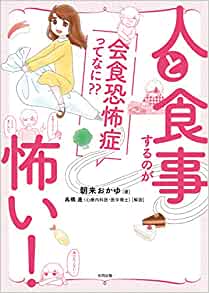 �@�w
�@�w �@�w
�@�w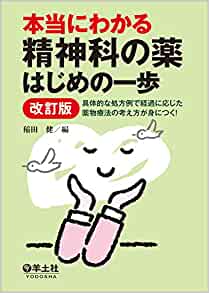
 �@�w
�@�w