 |
������S�@�i�����̋@�\�ƕa�C�ƌ��o�P�A�j |
 |
mail�Finfo@aofc-ydc.com
|
��Q�̂���l�̈�Âƕ������x����@���x
|
 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ |
|
|
| ��Q�̂���l�̈�Âƕ������x����@���x |
�͂��߂ɁF��Q�ҕ����̊�{���O
�@�@
�@�i�P�j��{���O
�@�@�@�@�@��Q�ҕ����̊�{���O�́A�Ⴊ��������l�ƂȂ��l�������ł��B
�@�@�@�@�@��Q�̂���l�̈�Âƕ������x����@���x�����鎖�ɂ������L�̗��O������������܂��B
�@�i�Q�j�Ⴊ���ҕ����̗��O����������e��̖@�ߓ�
�@�@�@�@�@�Ⴊ���҂̈�Â╟���́A���̗l�ȏ��A�@�߁A�錾���ɂ���Ďx�����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�P�F���ۏ��
�@�@�@�@�@�Q�F�e��̖@��
�@�@�@�@�@�R�F�錾�Ȃ�
�@�i�R�j��Q����ΏۂƂ����{�݁E����--�����s�̏ꍇ
�@�@�@�@�@����24�N���玙�������@�Ɋ�Â���Q����ΏۂƂ����{�݁E���Ƃ��ς��A�{�ݑ̌n�ɂ��āA�ʏ��E������
�@�@�@�@�@���p�`�Ԃ̕ʂɂ��ꌳ������Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�܂��A18�Έȏ�̏�Q���{�ݓ����҂ɂ��ẮA��Q�ґ����x���@�̏�Q�Ҏ{��őΉ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@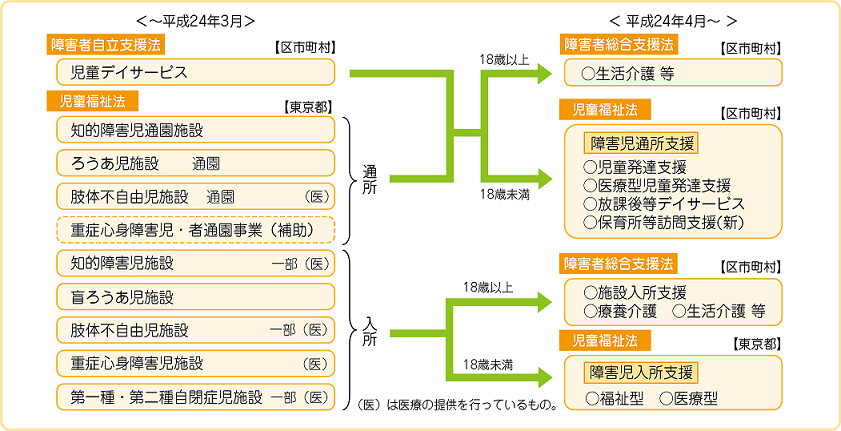
1�F���ۏ��
�@�@�@���@�ɖ��L����Ă���悤�ɁA�������ꂽ���ۏ��͕K����������炷��`��������܂��B
�@�i�P�j���{�����@��X�W���ƍ��ۏ��
�@�@�@�@�@���̌��@�́A���̍ō��@�K�ł��āA���̏��K�ɔ�����@���A���߁A�ْ��y�э����Ɋւ��邻�̑��̍s�ׂ�
�@�@�@�@�@�S�����͈ꕔ�́A���̌��͂�L���Ȃ��B
�@�@�@�@�@���{���������������i��F���A���́j�y�ъm�����ꂽ���ۖ@�K�́A����𐽎��ɏ��炷�邱�Ƃ�K�v�Ƃ���B
�@�i�Q�j���A�̏�Q�Ҍ������@�i2014�N��y�j �iCRPD : Convention on the Rights and Persons with Disabilities�j�@ �@�@
�@�@�@��Q�Ҍ������Ƃ��@�@�@�@
�@�@�@�@�@��Q�̂���l�̊�{�I�l���𑣐i�E�ی삷�邱�ƁA�ŗL�̑����̑��d�����i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��鍑�ۓI�����ŁA �@�@
�@�@�@�@�@2006�N��61�A����ɂ����č̑�����܂����B
�@�@�@�@�@���̏��Ɋ�Â��ē��{�����̏Ⴊ���҂Ɋւ���@�߂���������܂����B �@
�@�@�@�ړI
�@�@�@�@�@��Q�҂��l���y�ъ��{�I���R�̋��L���m�ۂ���B �@�@�@�@
�@�@�@�@�@��Q�҂̌ŗL�������̑��d�𑣐i����B �@
�@�@�A��ȓ��e
�@�@�@�@�@��Q�Ɋ�Â����������ʂ̋֎~�i�����I�z���̔ے���܂ށj �@
�@�@�@�@�@��Q�҂��Љ�ɎQ�����A��e����邱�Ƃ𑣐i �@�@
�@�@�@�@�@���̎��{���Ď�����g�g�݂̐ݒu
�Q�F��Q�҂Ɋ֘A����@��
�@�i���j�֘A����@���ꗗ
�@�@�@�@�i�P�j���������@�i1947�N�j
�@�@�@�@�i�Q�j�g�̏�Q�ҕ����@�i1949�N�j
�@�@�@�@�i�R�j���_�ی������@�i1950�N�j
�@�@�@�@�i�S�j�m�I��Q�ҕ����@�i1960�N�j
�@�@�@�@�i�T�j��Q�Ҋ�{�@�i1970�N�j
�@�@�@�@�i�U�j���B��Q�Ҏx���@�i2004�N�j
�@�@�@�@�i�V�j��Q�ґ����x���@�i2005�N�j
�@�@�@�@�i�W�j��Q�ҋs�Җh�~�@�i2012�N�j
�@�@�@�@�i�X�j��Q�җD�撲�B���i�@�i2012�N�j
�@�@�@�@(10)��Q�ҍ��ʉ����@�i2016�N�j
�@�i���j�Љ���Z�@
�@�@�@�@�@���{�ɂ����鐶���ی�@�A���������@�A��q�y�ѕ��q���тɉǕw�����@�A�V�l�����@�A�g�̏�Q�ҕ����@�A
�@�@�@�@�@�m�I��Q�ҕ����@�̑��́B
�@�@�@�@�@�P�������Z�@�Ƃ������܂��B
�@�@�@�@�@�����ی�@�i1950�N�{�s�j
�@�@�@�@�@���������@�i1947�N�{�s�j
�@�@�@�@�@��q�y�ѕ��q���тɉǕw�����@�i1964�N�{�s�B���͕̂�q�����@�A��q�y�щǕw�����@�j
�@�@�@�@�@�V�l�����@�i1963�N�{�s�j
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�i1949�N�{�s�j
�@�@�@�@�@�m�I��Q�ҕ����@�i1960�N�{�s�j
�@�i�P�j���������@�i1947�N�j
�@�@�@���������@�Ƃ��̖ړI��
�@�@�@�@�@�����̕�����S��������I�@�ւ̑g�D��A�e��{�y�ю��ƂɊւ����{�������߂���{���@���ł��B
�@�@�@�@�@�Љ���Z�@��1�B
�@�@�A�Ώێ�
�@�@�@�@�@���������@��̎����ɂ��ẮA�J����@��18�Ζ�����N���҂Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Q�l�Ƃ��āA������ЂƂ�
�@�@�@�@�@�ی�N��ƍl���A18�Ζ����Ƃ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@��Q���ɂ��Ă��A��Q�̂���u�����v�Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@���s�͌���18�i�Œ���22�j������ł����A�N��ŋ�炸�A�{�݂⎩���̂������\�Ɣ��f���������܂�
�@�@�@�@�@�x���𑱂���l�ɕύX����܂����B
�@�@�@�@�@�@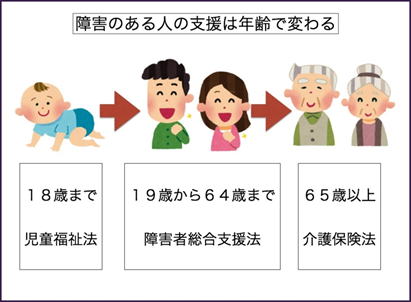
�@�i�Q�j�g�̏�Q�ҕ����@�i1949�N�j
�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�Ƃ�
�@�@�@�@�@��Q�҂̓��퐶���y�юЉ���𑍍��I�Ɏx�����邽�߂̖@��(�����\���N�@����S��\�O��)�Ƒ��܂��āA
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߁A�g�̏�Q�҂��������A�y�ѕK�v�ɉ����ĕی삵�A
�@�@�@�@�@���Đg�̏�Q�҂̕����̑��i��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���A�Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�A�ړI�@�@
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂̎����B �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂̎Љ�o�ϊ����̎Q���B�@
�@�@�B�g�̏�Q�҂̒�`
�@�@�@�@�@18�Έȏ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t---A1:�ŏd�x�AA2:�d�x�AB1:���x�AB2:�y�x
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�@��l���ɋK�肳��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂Ƃ́A �g�̏�̏�Q�������\���Έȏ�ŁA�s���{���m������g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t��
�@�@�@�@�@�@�@�@�ׂ���Ă�����B
�@ �D�g�̏�Q�̎�ށi�g�̏�Q�ҕ����@�j
�@�@�@�@�@���o��Q
�@�@�@�@�@���o�܂��͕��t�@�\��Q
�@�@�@�@�@�����@�\�E����@�\�E�@�\��Q
�@�@�@�@�@���̕s���R�F�㎈�A�����A�̊� �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@���c�����ȑO�̔�i�s���̔]�a�ςɂ��^���@�\��Q
�@�@�@�@�@������Q�i���������j
�@
�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u���o��Q�v�A�u���o��Q�v�A�u�����E�����Q�v�A�u������Q�v��
�@�@�@�⑫�F���̕s���R �@
�@�@�@�@�@�㎈�A�����i1�`7���j �̊��i1�C2�C3�C5���j
�@�@�@�@�@�㎈�@�\��Q�i1�`7���j
�@�@�ړ��@�\��Q�i1�`7���j
�@
�@�@�@�@�@����̎w�������ҁ�2�� ����̐e�w�Ɛl�����w��������3��
�@�@�@�⑫�F������Q
�@�@�@�@�@������Q�Ƃ́A�������̎����ŁA���퐶�����������������������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@�\��Q�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�t���@�\��Q�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�ċz��@�\��Q�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�N���܂��͒����@�\��Q�E�����@�\��Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�̑��@�\��Q�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�B���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q�@
�@�@�@�@�@�@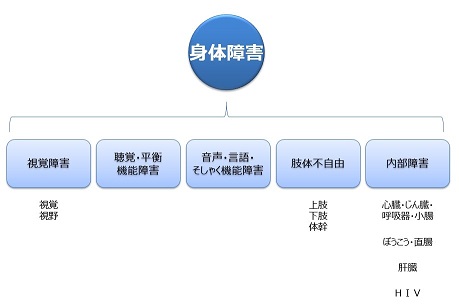
�@�i�R�j���_�ی������@�i1950�N�j
�@�@�@���_�ی������@�Ƃ�
�@�@�@�@�@���_��Q�҂̈�ÁE�ی�A���̎Љ�A�̑��i�E�����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���̑��i�̂��߂̕K�v�ȉ����A
�@�@�@�@�@���̔����̗\�h���̑������̐��_�I���N�̕ێ��y�ё��i�ɂ��A���_��Q�҂̕����̑��i�E�����̐��_�ی�
�@�@�@�@�@�̌����}�邱�Ƃɂ���A�Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�A�ړI�@�@�@
�@�@�@�@�@���_��Q�҂̈�� �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�ی�E�Љ�o�ϊ����̎Q�����i
�@�@�B�K����e�@
�@�@�@�@�@���_��Q�҂̒�`---�@���ɂ���Ď�ΏۂƂȂ�a�C������Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@���_�a�@�A���_�ی������Z���^�[�̒�`�B�@�@ �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@���_�ی��w���Ɠ��@�E�����ɂ��āB�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�Љ�A�{�݁A�K��w���ɂ��āB
�@�@�@�⑫�P�F���_�ی��y�ѐ��_��Q�ҕ����Ɋւ���@���ɂ����鐸�_��Q�҂̒�` �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������� �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_��p�����ɂ��}�����Ŗ��͂��̈ˑ��� �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�I��Q �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�a�� �@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̑��̐��_������L����҂������B�i���B��Q���܂ށj
�@�@�@�⑫�Q�F���_��Q���_�ی������@�ɂ����鐸�_��Q�̒�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�I��Q�F���B���AIQ��75
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�m�ǁi�s���j�F���B���ȍ~
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ǁ@�F���_�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�o�ǁ@�@�@�@�F�X�g���X������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N���a�@�@�@�F�����Ƃ����J��Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���B��Q�F�L�Đ����B��Q�i���NJ֘A�j�A�w�K��Q�A���ӌ��ב�������Q�i�`�c�g�c�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@�@
�@�i�S�j�m�I��Q�ҕ����@�i1960�N�j
�@�@�@�m�I��Q�ҕ����@�Ƃ�
�@�@�@�@�@�m�I��Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߁A�m�I��Q�҉����E�ی��}��@���ł��B
�@�@�A�ړI
�@�@�@�@�@�m�I��Q�҂̎����ƎЉ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i���邽�߁A�m�I��Q�҂���������ƂƂ��ɕK�v�ȕی���s���A
�@�@�@�@�@���Ēm�I��Q�҂̕�����}�邱�ƁA�Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@��Q�Ҏ����x���@�i����17�N�j�Ƒ��܂��āA�m�I��Q�҂̎����̑��i�B �@
�@�@�@�@�@�Љ�o�ϊ����ւ̎Q���𑣐i �B�@
�@�@�@�@�@�m�I��Q�҂��������A�K�v�ȕی���s���i�X������j�A�m�I��Q�҂̕�����}��B
�@�@�@�@�@18�Έȏ�̒m�I��Q�҂̍X���̉����E�ی��B �@
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�X������̎��{�҂͎s�����ł��B
�@�@�B�K����e �@�@
�@�@�@�@�@�m�I��Q�ҋ�����x�����Ƃɂ���
�@�@
�@�@�@�@�@�{�݂ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�X���{�݁i�����ی�@�Ɋ�Â��ی�j �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@���Y�{�݁i�E�Ƃ�^���A�����j �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�����z�[���i�����Ɛݔ��A�����̕X���͂���A�ᗿ���A�Ǘ��l���K�v�j
�@�@�@�@�@�ڍׂ́A�u�m�I��Q�v��
�@�i�T�j��Q�Ҋ�{�@�i1970�N�j
�@�@�@��Q�Ҋ�{�@�Ƃ�
�@�@�@�@�@��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��Ɋւ��A��{�I���O���߁A�y�э��A�n�������c�̓���
�@�@�@�@�@�Ӗ��𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��̊�{�ƂȂ鎖�����߂邱��
�@�@�@�@�@���ɂ��A��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��𑍍��I���v��I�ɐ��i���A�����ď�Q�҂�
�@�@�@�@�@�����i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ���{�̖@���B �@
�@�@�A�ړI
�@�@�@�@�@��Q�҂̂��߂̎{��Ɋւ����{���O���߂邱�ƁB
�@�@�@�@�@��Q�҂̎����y�юЉ�Q���̎x�����̂��߂̎{��𑍍��I���v�悷�鎖�B
�@�@�@�@�@���E�n�������c�̂Ȃǂ̐Ӗ��m�ɂ��鎖�B�@
�@�@�B��{���O
�@�@�@�@�@���S�Q���ƕ����i�m�[�}���C�[�[�V�����j����{���O�ł��B
�@�@�C��Q�̒�`
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�A�m�I��Q�A���_��Q�i���B��Q���܂ށj�A���̑��̐S�g�̋@�\�̏�Q �i�ȉ��u��Q�v�Ƒ��̂���j��
�@�@�@�@�@����҂ł��āA��Q�y�юЉ�I��ǂɂ�� �p���I�ɓ��퐶�����͎Љ���ɑ����Ȑ��������Ԃɂ���
�@�@�@�@�@���̂������A�Ƃ���Ă��܂��B
�@�i�U�j���B��Q�Ҏx���@�i2004�N�@�����P�V�N�S���P���j
�@�@�@���B��Q�Ҏx���@�Ƃ�
�@�@�@�@�@�����A�w�K��Q�A���ӌ��ׁE��������Q�A�A�X�y���K�[�nj�Q�A���̑��̍L�Đ����B��Q�Ȃǂ̔��B��Q��
�@�@�@�@�@���҂ɑ��鉇�����ɂ��Ē�߂��@���B
�@�@�A���B��Q�Ƃ́H�i���B��Q�Ҏx���@�ɂ���`�j
�@�@�@
�@�@�@�@�@�ʏ��N��ɂ����Ĕ���������̂ŁA�����̂��̂��܂܂�܂��B
�@�@�@�@�@�P�j���X�y�N�g������ �@�@
�@�@�@�@�@�Q�j�A�X�y���K�[�nj�Q �@�@
�@�@�@�@�@�R�j���̑��̍L�Đ����B��Q �@�@
�@�@�@�@�@�S�j�w�K��Q �@�@
�@�@�@�@�@�T�j���ӌ��@��������Q�@ �@�@
�@�@�@�@�@�U�j���̑��@�i����ɗނ���]�@�\�̏�Q�j
�@
�@�@�B���B��Q�Ҏx���@�̖ړI
�@
�@�@�@�@�@���̖@���̎�|�Ƃ��āA�ȉ����f�����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�P�j���B��Q�𑁊��ɔ������A���B�x�����s�� �@
�@�@�@�@�@�Q�j�w�Z����ɂ����锭�B��Q�҂ւ̎x�� �@
�@�@�@�@�@�R�j���B��Q�҂̏A�J�̎x�� �@�@
�@�@�@�@�@�S�j���B��Q�҂̐����S�ʂɂ킽��x�� �@�@
�@�@�@�@�@�T�j���B��Q�҂̉Ƒ��ւ̎x�� �@�@
�@�@�@�@�@�U�j���y�ђn�������c�̂̐Ӗ��𖾂炩�ɂ��� �@�@
�@�@�@�@�@�V�j���B��Q�Ҏx���Z���^�[�̎w��
�@�@�C���B��Q�Ҏx���@�̋K����e �@
�@�@�@�@�@���B��Q�̒�`�Ɩ@�I�Ȉʒu�Â� �@
�@�@�@�@�@���c�������琬�l���܂ł̒n��ɂ������т����x���̑��i�@�@�@ �@
�@�@�@�@�@���Ƃ̊m�ۂƊW�҂ٖ̋��ȘA�g�̊m�ہ@�@�@ �@
�@�@�@�@�@�q��Ăɑ��鍑���̕s���̌y��
�@
�@�@�D���B��Q�Ҏx���@�̔w�i
�@�@�@�@�@�ȉ��̖��_���������邽�߂ɐ��肳��܂����B
�@�@�@�@�@���B��Q�́A�l���ɐ�߂銄���͍����i���ʃN���X�ݐЎ҂̂U���j�D
�@�@�@�@�@�@���x���Ȃ��A���x�̒J�Ԃł����B �@
�@�@�@�@�@�]���̎{��ł͏\���ȑΉ����Ȃ���Ă��܂���ł����B�@�@ �@
�@�@�@�@�@���B��Q�Ɋւ�����Ƃ͏��Ȃ��D �@
�@�@�@�@�@�n��ɂ�����W�҂̘A�g���s�\���Ŏx���̐��������Ă��܂���ł����B�@�@ �@
�@�@�@�@�@�Ƒ��́A�n��ł̎x�����Ȃ��傫�ȕs��������Ă��錻�L��܂����B
�@�i�V�j��Q�ґ����x���@�i2005�N�j
�@�@�@��Q�ґ����x���@�Ƃ��@�@
�@�@�@�@�@��Q�̂���l����{�I�l���̂���l�Ƃ��Ă̑����ɂӂ��킵�����퐶����Љ�����c�ނ��Ƃ��ł���悤�ɁA
�@�@�@�@�@�K�v�ƂȂ镟���T�[�r�X�Ɋւ�鋋�t�E�n�搶���x�����Ƃ₻�̂ق��̎x���������I�ɂ����Ȃ����Ƃ��߂�
�@�@�@�@�@�@���ł��B
�@�@�@�@�@�@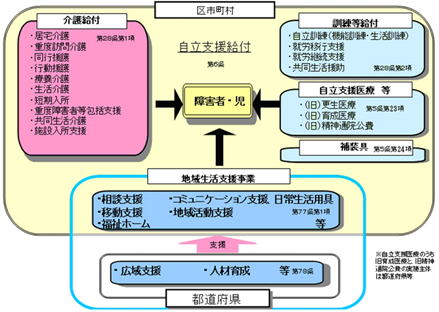
�@�@�A�ړI
�@�@�@�@�@��Q�ҋy�я�Q������{�I�l�������L����l�Ƃ��Ă̑����ɂӂ��킵�����퐶�����͎Љ�����c�ނ��Ƃ�
�@�@�@�@�@�ł���悤�A�K�v�ȏ�Q�����T�[�r�X�ɌW�鋋�t�A�n�搶���x�����Ƃ��̑��̎x���𑍍��I�ɍs���A�����ď�Q��
�@�@�@�@�@�y�я�Q���̕����̑��i��}��ƂƂ��ɁA��Q�̗L���ɂ�����炸���������݂ɐl�i�ƌ��d�����S���ĕ�炷
�@�@�@�@�@���Ƃ̂ł���n��Љ�̎����Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂��B
�@�@�@�@�@�@
�@�@�B�K����e
�@�@�@�@�@�Ώێ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҁA�m�I��Q�ҁA���_��Q�ҁA ��a
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�s�����\������Q�x���敪�ɉ������x�����܂��B
�@�@�@�@�@�@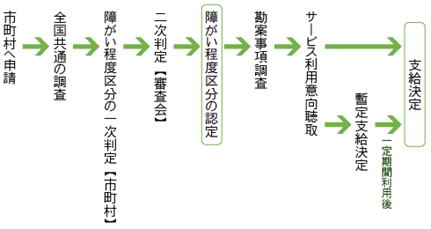
�@�i�W�j��Q�ҋs�Җh�~�@�i2012�N�j
�@�@�@��Q�ҋs�Җh�~�@�Ƃ�
�@�@�@�@�@��Q�҂̑��������A������Љ�Q���̖W���ƂȂ�Ȃ��悤�s�҂��֎~����ƂƂ��ɁA�����\�h�Ƒ��������̂���
�@�@�@�@�@�̎��g�݂�A��Q�҂����ɗ{�삷��l�ɑ��Ďx���[�u���u���邱�ƂȂǂ��߂����̂ł��B
�@�@
�@�@�A�ړI
�@�@�@�@�@��Q�ҋs�҂̖h�~���̂��߂̐Ӗ����ۂ��ƂƂ��ɁA��Q�ҋs�҂����Ǝv�����Q�҂������҂ɑ���
�@�@�@�@�@�ʕ�`�����ۂ��ȂǂŁA��Q�҂̑�������鎖�ł��B
�@�@�B�K����e
�@�@�@�@�@�S���̎s������s���{���́A��Q�ҋs�҂Ɋւ��鑋����ݒu���A���k��ʕ�Ȃǂ̎�t��s�҂̑���������
�@�@�@�@�@��Q�҂̕���s������̒ʕ�⑊�k���āA�s������s���{���Ȃǂ̊W�@�ւ��A��Q�҂̈ꎞ�ی��
�@�@�@�@�@�{��҂ɑ��镉�S�y���̂��߂̎x���ȂǕK�v�ȑ[�u���s���܂��B
�@�@����Q�ҋs�҂̗�
�@�@�@�@�@�@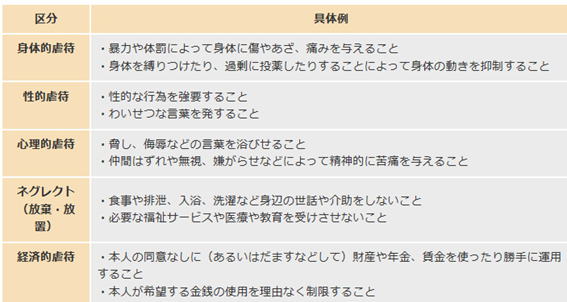
�@�i�X�j��Q�җD�撲�B���i�@�i2012�N�j
�@�@�@�ړI
�@�@�@�@�@��Q�҂̌o�ϓI�Ȏ����𑣂����߁A ���⎩���̂ɑ��A��Q�ҏA�J�{�݂Ȃǂ֕��i��Ɩ�������w�͂�
�@�@�@�@�@���߂�B
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@
�@(10)��Q�ҍ��ʉ����@�i2016�N�j
�@�@�@��Q�ҍ��ʉ����@�Ƃ�
�@�@�@�@�@���������́A��Q�𗝗R�Ƃ��鍷�ʂ̉����̐��i�Ɋւ���@���A�ł��B
�@�@�@�@�@
�@�@�A�ړI
�@�@�@�@�@��Q�҂ɑ��āA��Q�𗝗R�Ƃ��āA���ʂ��邱�Ƃ�A���̑��̌������v��N�Q����s�ׂ̋֎~��ړI��
�@�@�@�@�@���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�s���ȍ��ʓI�戵���̋֎~���s����
�@�@�@�@�@�����I�z���̒��s����
�@�@�@�@�@�����I�z���Ƃ́A�����A��ЁA���X�Ȃǂ̎��Ǝ҂ɑ��āA��Q�̂���l����A�Љ�̒��ɂ���o���A����菜��
�@�@�@�@�@���߂ɉ��炩�̑Ή���K�v�Ƃ��Ă���Ƃ̈ӎv���`����ꂽ���ɁA���S���d�����Ȃ��͈͂őΉ����邱�Ƃ����߂�
�@�@�@�@�@�Ȃǂł��B
�@�@�@�@�@�@
�R�F���̑��̐鐾����
�@�i�P�j�q�|�N���e�X�̐���
�@�@�@�q�|�N���e�X�̐����Ƃ�
�@�@�@�@�@��t�̗ϗ��E�C���Ȃǂɂ��ẮA�M���V�A�_�ւ̐鐾���B
�@�@�@�@�@����̈�×ϗ��̍����𐬂����҂̐����E���N�ی�̎v�z�A ���҂̃v���C�o�V�[�ی�̂ق��A���ƂƂ��Ă�
�@�@�@�@�@�����̕ێ��A �k�퐧�x�̈ێ���E�\�̕����ێ��Ȃǂ�搂��Ă���B
�@�@�@�@�@�q�|�N���e�X
�@�@�@�@�@�@�@�I���O460�N����`�I���O370�N����̌Ñ�M���V�A�̈�ҁB
�@�@�@�@�@�@�@�d�v�Ȍ��т̂ЂƂɁA��w�����n�I�Ȗ��M���p����藣���A�Տ��Ɗώ@���d��o���Ȋw�ւƔ��W
�@�@�@�@�@�@�@���������Ƃ��������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@����Ɉ�t�̗ϗ����Ƌq�ϐ��ɂ����w�����x�Ƒ肵�����͂��S�W�Ɏ��߂��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@���݂ł��w�q�|�N���e�X�̐����x�Ƃ��Ďp����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@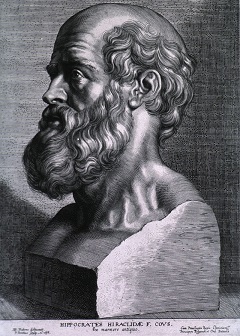
�@�@�A�q�|�N���e�X�̐����S��
�@�@�@�@�@��̐_�A�|�����A�A�X�N���[�s�I�X�A�q�M�G�C�A�A�p�i�P�C�A�A�y�ёS�Ă̐_�X��B
�@�@�@�@�@�����g�̔\�͂Ɣ��f�ɏ]���āA���̐������邱�Ƃ𐾂��B
�@�@�@�@�@���̈�p�������Ă��ꂽ�t�����̐e�̂悤�Ɍh���A����̍��Y���^���āA�K�v���鎞�ɂ͏�����B
�@�@�@�@�@�t�̎q�������g�̌Z��̂悤�Ɍ��āA�ނ炪�w��Ƃ���Ε�V�Ȃ��ɂ��̏p��������B
�@�@�@�@�@�����u�`���̑���������@�ŁA��p�̒m�����t�⎩��̑��q�A�܂��A��̋K���ɑ����Đ���Ō���Ă���
�@�@�@�@�@��q�B�ɕ������^���A����ȊO�̒N�ɂ��^���Ȃ��B
�@�@�@�@�@���g�̔\�͂Ɣ��f�ɏ]���āA���҂ɗ�����Ǝv�����Ö@��I�����A�Q�ƒm�鎡�Ö@�������đI�����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�˗�����Ă��l���E�����^���Ȃ��B
�@�@�@�@�@���l�ɕw�l�𗬎Y�����铹���^���Ȃ��B
�@�@�@�@�@���U�������Ɛ_�����т��A��p���s���B
�@�@�@�@�@�ǂ�ȉƂ�K��鎞�������̎��R�l�Ɠz��̑�����킸�A�s����Ƃ����ƂȂ��A��p���s���B
�@�@�@�@�@��Ɋւ��邩�ۂ��Ɋւ�炸�A���l�̐����ɂ��Ă̔閧�����炷��B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@���̐�������葱�������A���͐l���ƈ�p�Ƃ����A�S�Ă̐l���瑸�h�����ł��낤�I
�@�@�@�@�@�������A������A���̐�����j�鎞�A���͂��̔��̉^�������邾�낤�B
�@�i�Q�j�W���l�[�u�錾
�@�@�@�W���l�[�u�錾�Ƃ�
�@�@�@�@�@1948�N9���̑�2�E��t���ŋK�肳�ꂽ��̗ϗ��Ɋւ���K���B
�@�@�@�@�@ �q�|�N���e�X�̐����̗ϗ��I���_���A���㉻�E�������������̂ł���B
�@�@�@�@�@1968�N�A1984�N�A1994�N�A2005�N�A2006�N�̉�����o�āA���݂�2017�N�łɎ���B
�@�@�A2006�N�ł̃W���l�[�u�錾�S��
�@�@�@�@�@�S���U��l���̂��߂ɕ����� �E�l���I����ɂ̂��Ƃ�A������H����B�i�����I�E�ǎ��I�z���j
�@�@�@�@�@�l�����ő���ɑ��d����B�i�l���̑��d�j
�@�@�@�@�@���҂̌��N����ɍl������B
�@�@�@�@�@���҂̔閧�����炷��B�i���`���j
�@�@�@�@�@���҂ɑ��č��ʁE�Ό������Ȃ��B�i���҂̔ʁj
�@�i�R�j�w���V���L�錾
�@�@�@�w���V���L�錾�Ƃ�
�@�@�@�@�@1964�N�C���E��t���ō̑����ꂽ�A�q�g��ΏۂƂ��鐶����w�I�����Ɍg����t�̂��߂̊����ł��B
�@�@�@�@�@������w�I�����́A�ŏI�I�Ƀq�g��ΏۂƂ��������ɂ��Ȃ���A���ۂ̈�ÂɊ�^������̂ɂȂ�܂���B
�@�@�@�@�@���݂̗Տ������́C1964�N�̃w���V���L�錾��ϗ��I��ՂƂ��Ă���D
�@�@�@�@�@���̃w���V���L�錾�̏d�v�Ȍ����Ƃ��āA�q�g��ΏۂƂ���Տ����������{���邽�߂ɂ́C���̂R���ڂ��K�{
�@�@�@�@�@�Ƃ���Ă���D
�@�@�A�w���V���L�錾�̏d�v�ȂR����
�@�@�@�@�@�@1�j�Ȋw�I�E�ϗ��I�ɓK���Ȕz�����L�ڂ����������{�v�揑���쐬���邱���B
�@�@�@�@�@�@2�j�����R���ψ���Ŏ����v��̉Ȋw�I�E�ϗ��I�ȓK���������F����邱�ƁB �@
�@�@�@�@�@�@3�j�팱�҂ɁC���O�ɐ���������p���Ď����v��ɂ��ď\���ɐ������A�����ւ̎Q���ɂ��Ď��R�ӎv��
�@�@�@�@�@�@�@�@��铯�ӂ��ɓ��邱�ƁB
�@�@�@�@�@�킪���ɂ����Ă�1990�N����A�w���V���L�錾�̐��_�Ɋ�Â������i�̗Տ������̎��{�Ɋւ������A
�@�@�@�@�@�{�s����Ă��܂��B
�@�@�⑫�F�C���t�H�[���h�E�A�Z���g�iinformed assent�j
�@�@�@�@�@�q�ǂ��̊��ҁi�����j�Ɏ��Â⌟���̐������s���A�q�ǂ��{�l�̓��ӂ����Ƃł��B
�@�@�@�@�@��ʂɐ��l���҂ł́A����\�͂̂��鎩�������l��ΏۂƂ����A�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�����{����܂��B
�@�@�@�@�@�]���A���҂��q�ǂ��̏ꍇ�́A�ی�҂Ȃǂ̑���҂ɃC���t�H�[���h�E�R���Z���g���s���Ă��܂����B
�@�@
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�������A1994�N���q�ǂ��̌����������y�����ȂǁA���{�ł��q�ǂ��ɑ��錠���̑��d�����߂���悤��
�@�@�@�@�@�Ȃ��Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�A�Z���g�͓��ӂƂ���܂����A��Ăւ̎^���A���F�Ƃ������Ӗ���������������A�����̖@�I�ʒu�Â���A
�@�@�@�@�@����\�͂ɔz�����A�Ȃ�ׂ������I�ɓ��ӂ����邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�Ⴆ�A�q�ǂ��������ł���悤�ɗp��Ղɂ�����A�G�Ȃǂ�p���Đ�������H�v���Ȃ���Ă��܂��B
�@�i�S�j���X�{���錾�@�P�X�W�P�N
�@�@�@���X�{���錾�Ƃ�
�@�@�@�@���҂̌����Ɋւ�����̂𐢊E��t��(WMA)���錾�������̂ł��B
�@�@�@�@�P�j���҂́A�����̈�t�����R�ɑI�Ԍ�����L����B
�@�@�@�@�Q�j���҂́A����O������̊������Ɏ��R�ɗՏ��I����їϗ��I���f��������t�̎��ÊŌ���錠��
�@�@�@�@�@�@��L����B
�@�@�@�@�R�j���҂͏\���Ȑ���������ɁA���Â�����邩�܂��͋��ۂ��錠����L����B
�@�@�@�@�S�j���҂́A�����̈�t�����҂Ɋւ��邠�����w�I�ȏڍׂȎ����̋@���I�Ȑ����d���邱�Ƃ����҂���
�@�@�@�@�@�@������L����B
�@�@�@�@�T�j���҂́A�����������Ď����}���錠����L����B
�@�@�@�@�U�j���҂́A�K���ȏ@���̐��E�҂̏������ӂ��ސ��_�I����ѓ����I�Ԃ߂��邩�A�܂��͂����f��錠����
�@�@�@�@�@�@�L����B
|
| �Q�l���� |
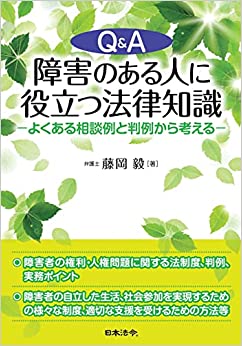 �@�wQ&A ��Q�̂���l�ɖ𗧂@���m���x �@�wQ&A ��Q�̂���l�ɖ𗧂@���m���x
 �@�w����Ŋw�Ԕ��B��Q�̖@���g���u��Q&A�x �@�w����Ŋw�Ԕ��B��Q�̖@���g���u��Q&A�x
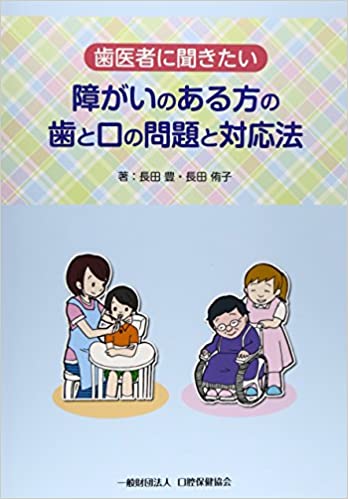 �@�@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@�@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x
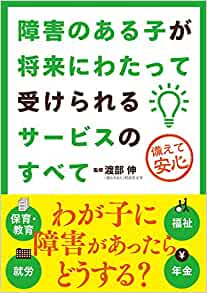 �@�w��Q�̂���q�������ɂ킽���Ď���T�[�r�X�̂��ׂ��x �@�w��Q�̂���q�������ɂ킽���Ď���T�[�r�X�̂��ׂ��x
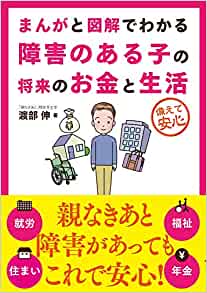 �@�w�܂Ɛ}���ł킩���Q�̂���q�̏����̂����Ɛ����x �@�w�܂Ɛ}���ł킩���Q�̂���q�̏����̂����Ɛ����x
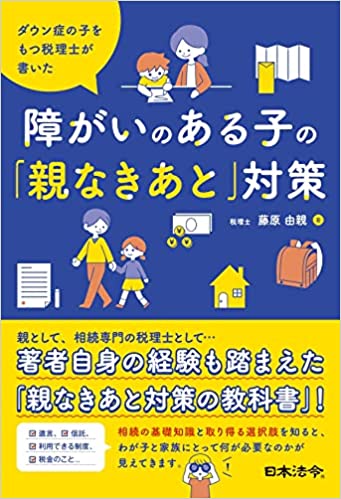 �@�w�_�E���ǂ̎q�����ŗ��m�������� ��Q�̂���q�́u�e�Ȃ����Ɓv���x �@�w�_�E���ǂ̎q�����ŗ��m�������� ��Q�̂���q�́u�e�Ȃ����Ɓv���x
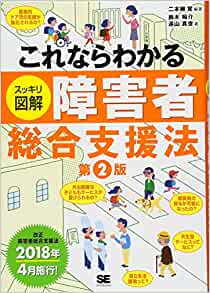 �@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r ��Q�ґ����x���@ ��2���x �@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r ��Q�ґ����x���@ ��2���x
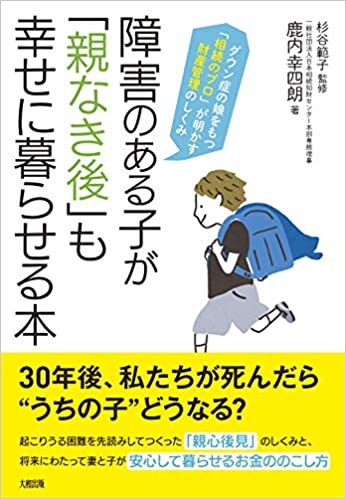 �@�w��Q�̂���q���u�e�Ȃ���v���K���ɕ�点��{ �_�E���ǂ̖������u�����̃v���v�����������Y�Ǘ��̂������x �@�w��Q�̂���q���u�e�Ȃ���v���K���ɕ�点��{ �_�E���ǂ̖������u�����̃v���v�����������Y�Ǘ��̂������x
|
|

|
copyrightc 2021 YDC all rights reserved
mail�Fmail�Finfo@aofc-ydc.com
|
|


 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@

 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@