 |
������S�@�i�����̋@�\�ƕa�C�ƌ��o�P�A�j |
 |
mail�Finfo@aofc-ydc.com
|
�^����Q�ɂ���
|
 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@ �@�@ |
|
|
| �g�̏�Q |
�P�F�g�̏�Q�ɂ���
�@�i�P�j�g�̏�Q�Ƃ�
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�Ƃ́A��V�I���邢�͌�V�I�ȗ��R�Őg�̋@�\�̈ꕔ�ɏ�Q���Ă����ԁA���邢�͂��̂悤��
�@�@�@�@�@��Q���̂̂��Ƃ������܂��B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�i1947�N�{�s�j�̑�2��-��4���ɂ����Ă͎��̗l�ɒ�`����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�҂Ƃ́A�g�̏�̏�Q������\���Έȏ�̎҂ł��āA�s���{���m������g�̏�Q�Ҏ蒠�̌�t��
�@�@�@�@�@�����̂������A�Ƃ���Ă��܂��B
�@�i�Q�j�g�̏�Q�҂Ɛg�̏�Q��
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�͌����Ƃ�����18�Έȏオ�Ώ��ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@��18�Ζ����̏ꍇ�͎��������@�Ɋ�Â��Ĉꕔ�g�̏�Q�ҕ����@�̓K�p���A�܂����������@���̂ł��ʂ�
�@�@�@�@�@�����{����u���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@���̂��ߓ�����Q�҂ł����Ă��A��18�����Ɏx���̓��e�◘�p�\�Ȏ{�݂��قȂ邱�Ƃ�����B
�@�@�@�@�@�Ώێ҂��w���ď̂���18�Έȏ�͐g�̏�Q���ƌĂсA��18�Ζ����͐g�̏�Q���ƌĂт܂��B
�@�@�@�@�@������m�I��Q�̏ꍇ�����l�ł��B
�Q�F�g�̏�Q�̎�ށi�g�̏�Q�ҕ����@�j
�@�i�P�j���o��Q
�@�@�@�@�@���o��Q�͗l�X�ȗv�����炭�����͂̒ቺ���m���Ă��܂����A���삪�����Ȃ����싷�������o��Q�ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�@�i�Q�j���o�܂��͕��t�@�\��Q
�@�@�@�@�@���o��Q�҂͐g�̏�Q�҂̂����A���o��Ɋ��o�ݖ����钮�o��Q�i���͏�Q�j�����҂ł���A���o���Q��
�@�@�@�@�@�̈��ł��B
�@�@�@�@�@���o��Q�҂ɂ��낤�ҁi�W�ҁj�A�y�x����獂�x��Ȃǂ�����A�������Ă��璮�o�����������r�������A
�@�@�@�@�@����ɂ�蒮�͂��������V�l��������܂܂�܂��B
�@�@�@�@�@���t�@�\��Q�͎O���K�ǂ̋@�\��Q�₻�̑��̗v���ŋN������s�ɕK�v�ȃo�����X���ێ��ł��Ȃ���Q�ł��B
�@�@�@�@�@ �@���o��Q�҂̕����^�]����Ԃɕ\������}�[�N �@���o��Q�҂̕����^�]����Ԃɕ\������}�[�N
�@�i�R�j�����@�\�E����@�\�E�@�\��Q
�@�@�@�@�@�����@�\�̏�Q�Ƃ́A���������邽�߂̊튯�ł���A�����Ȃ��i���A���j�A�܂��͍A����\���튯�ɂȂ�炩��
�@�@�@�@�@��Q�����邽�߂ɘb�����Ƃɏ�Q�������Ԃł��B
�@�@�@�@�@����@�\�̏�Q�����o��Q�����邽�߂ɉ������ꂪ�l���ł����ɘb�����Ƃ��ł��Ȃ��A����ǂȂǂ�������
�@�@�@�@�@�Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�@�i�S�j�^����Q�i���̕s���R�F�㎈�A�����A�̊��j
�@�@�@�@�@�^����Q�́A���́A�����鍶�E�̎�i�㎈�j�A���E�̑��i�����j�܂��͑̊��ƌĂ�鋹���A�����A����
�@�@�@�@�@����Ȃ铷�̕����Ɍ��������邩�A�܂��͌������Ȃ��Ă��@�\��Q������A���퐶������ɐ������
�@�@�@�@�@�悤�ȏ�Q�̂��Ƃł��B�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@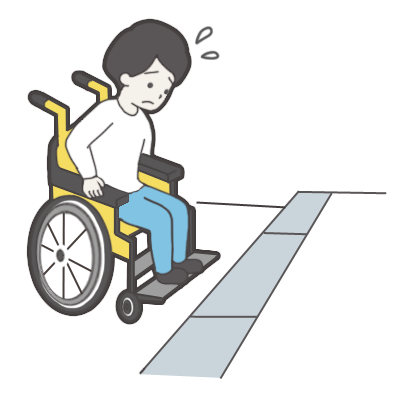
�@�i�T�j������Q�i���������j
�@�@�@�g�̏�Q�ҕ����@�ł͓�����Q�͌��݂̂Ƃ���A�S���@�\��Q�A�t���@�\��Q�A�ċz�@�\��Q�A�N���E�����@�\��Q�A
�@�@�@�����@�\��Q�A�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q�A�̑��@�\��Q��7�������Q�i�����@�\��Q�j�ƋK��
�@�@�@���Ă��܂��B�@
�@�@�@�@�@
�@�@�@�S���@�\��Q�i�S�s�S�j
�@�@�@�@�@
�@�@�A�t���@�\��Q�i�t�s�S�j
�@�@�@�@�@
�@�@�B�ċz��@�\��Q�i�ċz�s�S�j
�@�@�@�@�@
�@�@�C�N�����͒����@�\��Q
�@�@�@�@�@�@�@�l�H���
�@�@�@�@�@�@�@���
�@�@�@�@�@
�@�@�D�����@�\��Q
�@�@�@�@�@������ʐ؏����s�������E�a��
�@�@�@�@�@�@�@�㒰�Ԗ����ǕǏǁA�������P�]�ǁA��V���������ǁA�������A�L�͒��ǖ��_�o�ߏǁA�O��
�@�@�@�@�@���������ʼni���I�ɏ����@�\�̒������ቺ������
�@�@�@�@�@�@�@�N���[���a�A���ǃx�[�`�F�b�g�a�A����ِ�������ᇁA�������������ǏǁA��������������ǁA
�@�@�@�@�@�@�@�z���s�Ǐnj�Q
�@�@�E�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q
�@�@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�iHIV�j�͐l�Ԃ̃����p���ȂǂɊ������Ɖu�͂�ቺ�����A�ŏI�I�ɂ͌�V���Ɖu�s�S�nj�Q
�@�@�@�@�@�iAIDS�FAcquired�@Immuno-deficiency�@Syndrome�j�ǂ����܂��B
�@�@�@�@�@�Ɖu�͂��ቺ�A�܂��͕s�S�ƂȂ�ƁA���i�͊������Ȃ��悤�Ȕ���ȋۂȂǂɂ�銴���ǂ��N�����܂��B
�@�@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�ɂ��Ɖu�@�\��Q�̓q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�Ɋ������A���퐶���ɐ��������Ԃ��w���A
�@�@�@�@�@�P�`�S���ɋ敪����܂��B
�@�@
�@�@�F�̑��@�\��Q�i�̕s�S�E��㏞���̍d�ρj
�@�@�@�@�@
�R�F�g�̏�Q�Ɠ����@�@
�@�@�@�@�@�g�̏�Q�Ҏ蒠�͏�Q�̒��x�ɂ���ĂP?�V���̓���������܂��B
�@�@�@�@�@������7���܂ł���܂����A��t�̑ΏۂƂȂ�̂�6���ȏ��ŁA�����̏d����Q������ꍇ��1���J��オ�邽�߁A
�@�@�@�@�@�V���̏d����Q�ł�6���ƂȂ�A�蒠��t�̑ΏۂƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@�����́A�������������قǏd�x�ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@��ʓI�Ɏ��̗l�ɓ��������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@1�E2��---�d�x�i���ʏ�Q�ҁj�A
�@�@�@�@�@�@�@3�E4��---���x
�@�@�@�@�@�@�@5�E6��---�y�x�i���x�A�y�x�͈�ʏ�Q�ҁj
�@�@�@�@�@��ʂ́A�����Ƃ͕ʂɏ�Q�̒��x�������A��Ɍ�����ʋ@�ւ̊����̎��̊�ƂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@
�S�F�g�̏�Q�̉u�w
�i�P�j�g�̏Ⴊ���҂̓���
�@�@2018�N�i����30�N�j�x��Q�Ҍٗp���Ԓ������ʁv�i�����J���ȁj
�@�@�^����Q�i���̕s���R�j�� 42.0�����߁A�����œ����Ⴊ���� 28.1���A���o����Ⴊ���� 11.5���ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@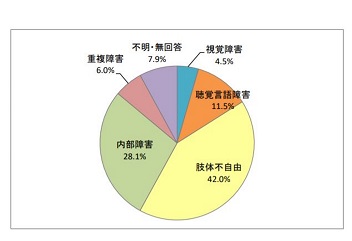
�i�Q�j�g�̏�Q�Ɖ^����Q�i���̕s���R�j
�@�@�@�@�g�̏�Q�ґ���436���l���A193���l�قǂ����̕s���R�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@���g�̏�Q�ҁF�ݑ��---�����J���ȁ@�u�����̂��Â炳�ȂǂɊւ��钲���v�@�i2016�N�j
�@�@�@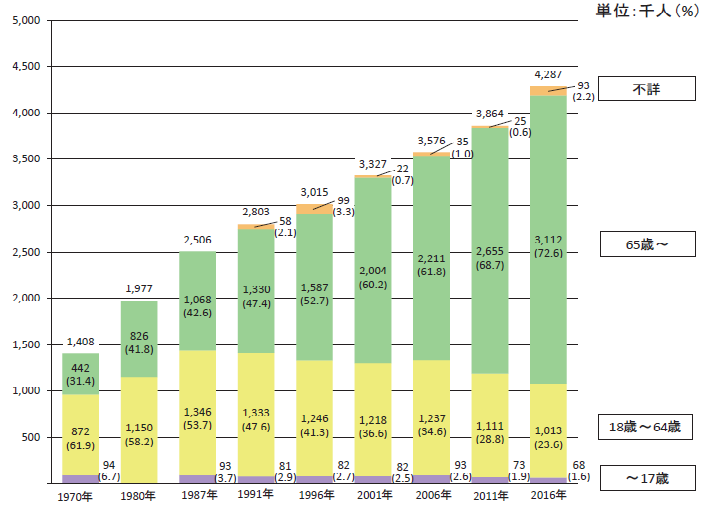
�@�@�@�g�̏�Q�́A65�Έȏ�̍���҂Œ����ɑ������Ă��܂��B
�⑫�F�g�̏�Q�Ɋ܂܂�Ȃ���Q
�@�@�@�@�@�k�o��Q�A�Ɋo��Q�A���o��Q
|
| �Q�l���� |
 �@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r��Q�ґ����x���@ ��2���x �@�w����Ȃ�킩��q�X�b�L���}���r��Q�ґ����x���@ ��2���x
 �@�w�V����ܔ� �g�̏�Q�F���y�єF��v��: ���߂Ɖ^�p�x �@�w�V����ܔ� �g�̏�Q�F���y�єF��v��: ���߂Ɖ^�p�x
 �@�w��Q�ґ����x���@ ��Q�x���敪�F��n���h�u�b�N �x �@�w��Q�ґ����x���@ ��Q�x���敪�F��n���h�u�b�N �x
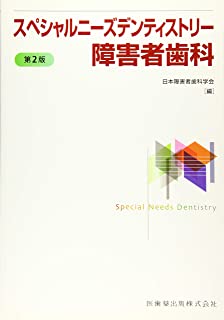 �@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2�Łx �@�w�X�y�V�����j�[�Y�f���e�B�X�g���[��Q�Ҏ��� ��2�Łx
 �@�wDSM-5�f�f�ʐڃ|�P�b�g�}�j���A���x �@�wDSM-5�f�f�ʐڃ|�P�b�g�}�j���A���x
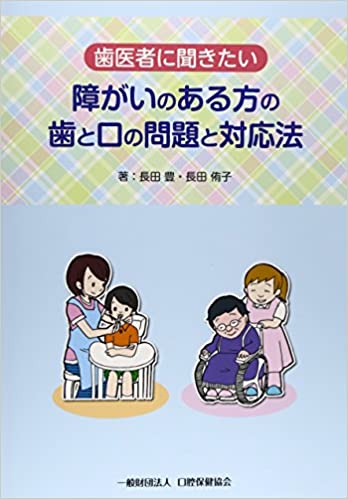 �@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x �@�w����҂ɕ������� �Ⴊ���̂�����̎��ƌ��̖��ƑΉ��@�x
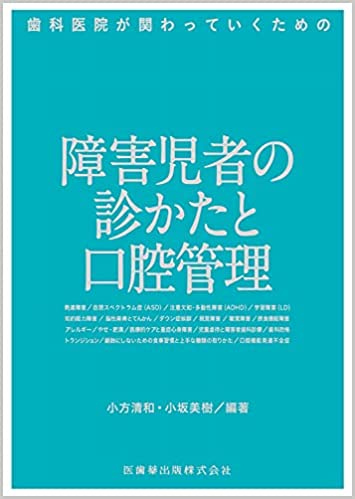 �@�w���Ȉ�@���ւ���Ă������߂̏�Q���҂̐f�����ƌ��o�Ǘ��x �@�w���Ȉ�@���ւ���Ă������߂̏�Q���҂̐f�����ƌ��o�Ǘ��x
 �@�w���ȉq���m�u�� ��Q�Ҏ��Ȋw ��2�� �x �@�w���ȉq���m�u�� ��Q�Ҏ��Ȋw ��2�� �x
|
| 22-3-20 |
|

|
copyrightc 2021 YDC all rights reserved
mail�Fmail�Finfo@aofc-ydc.com
|
|


 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@

 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@