| アデノウイルス感染症 () |
1:アデノウイルスとは
(1)アデノウイルスの生物学
二重鎖直鎖状DNAウイルスで、カプシドは直径約80nmの正20面体の球形粒子をしています。
エンベロープは持ちません。
カプシド(capsid)は、ウイルスゲノムを取り囲むタンパク質の殻のことを指します。
A〜Gの7種、52型に分類されます
アデノウイルスは感染性胃腸炎、ライノウイルス等とともに、風邪症候群を起こす主要病原ウイルスの一つです。
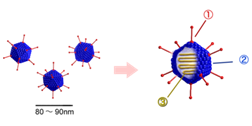 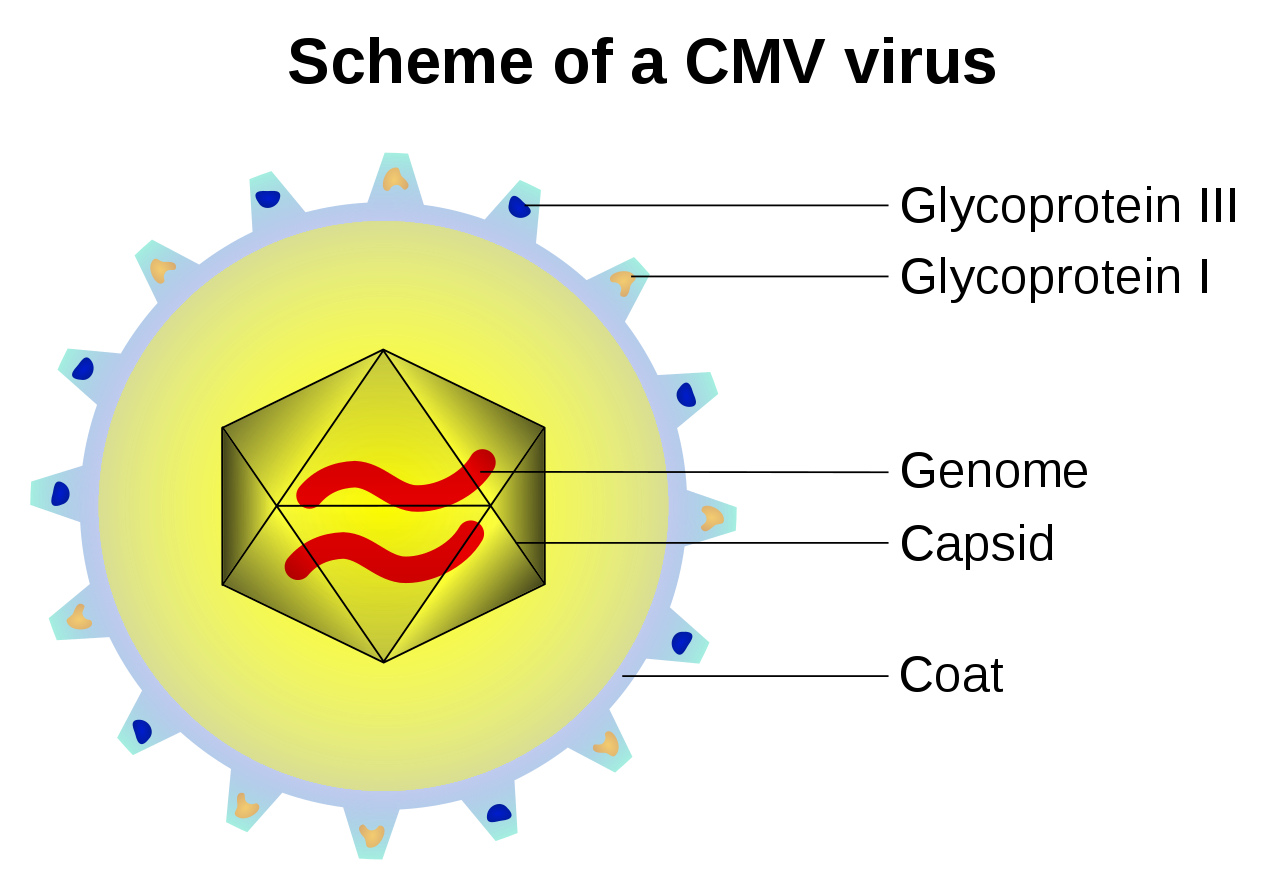 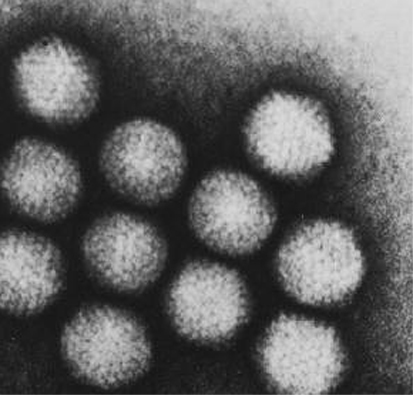
(2)病原性
咽頭炎などの呼吸器疾患や角結膜炎などの眼疾患をはじめとして、様々な疾患を引き起こします。
かぜ症候群の原因の一つですが、有効な薬はありません。
2:感染様式
(1)感染経路
便、飛沫、直接接触により感染します。
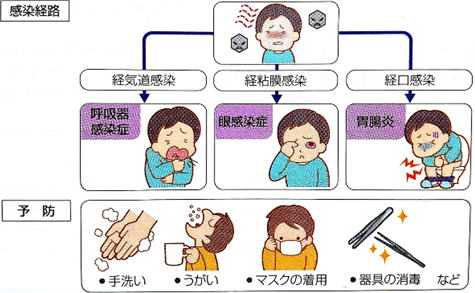
『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』 から引用
(2)潜伏期間
潜伏期は5〜7日です。
(3)増殖
感染した場合、アデノウイルスは扁桃腺やリンパ節の中で増殖します。
(アデノとは扁桃腺やリンパ節を意味する言葉です)
3:アデノウイルス感染症とその症状
(1)咽頭結膜熱(プール熱)
主として3・4型によります.
1日の間に39〜40度の高熱と、37〜38度前後の微熱の間を、上がったり下がったりします。
4〜5日ほど続き、扁桃腺が腫れ、のどの痛みを伴います。
その間、頭痛、腹痛や下痢を伴い、耳介前部および頸部のリンパ節が腫れることがあります.
夏のインフルエンザと呼ばれることもあります
(2)流行性角結膜炎 (EKC:epidemic kerato-conjunctivitis)
主として8、19、37型によるとされてきましたが、近年においては53、54、56型によるEKCが多発するように
なりました。
これらはいずれもD種アデノウイルスです。
目が充血し、目やにが出ますが、咽頭結膜熱のように高い熱はなく、のどの赤みも強くはありません。
結膜炎経過後に点状表層角膜炎を作ることが多く、幼小児では偽膜性結膜炎になることがあります
角膜混濁が発症することがあり、数か月以上も症状が残ることがあるので眼科での治療が必要です。
また全例ではありませんが、耳前リンパ節の腫脹を伴います。
流行性角結膜炎は伝染の恐れがなくなるまで(主要症状がなくなった後2日間)登校禁止となります。

結膜炎
充血し、眼脂(めやに)が出ます。
(ひどいときには「めやに」で目が開かないくらいになります)。
片目発症後、4〜5日後に反対側の目も発症する場合が多くあります。
涙目になったり、まぶたがはれることもあります。
視力が少し低下する場合があります。
症状が重くなると、耳前リンパ節が腫れて触ると痛みを伴います。
症状が強い人の場合は、まぶたの裏の結膜に白い膜ができ、眼球の結膜に癒着をおこします。
症状が治まるまで約2-3週間かかります。
角膜炎
透明な角膜に点状の小さな混濁が生じ、眼痛を感じます。
眩しさやかすみを感じます。
視力障害を感じることもあります。
黒目の表面がすりむける角膜びらんを伴い、目がゴロゴロしたり、眼痛がひどくなります。
症状が数ヶ月から丸一年に及ぶこともあります。
(3)肺炎・脳炎
主として3・7型によります。
特に7型は重症の肺炎を起こします。
乳幼児がかかることが多く、髄膜炎、脳炎、心筋炎などを併発することもあります。
だらだらと長引く発熱、咳、呼吸障害など重症になることがあり、時に致命的なことがあります
(4)胃腸炎
腸管アデノウイルス胃腸炎と呼ばれます。
主として31・40・41型によるものです。
潜伏期間は、3〜10日位です。
集団感染は食品中では増殖しないため、人から人への感染様式で広がります。
乳幼児期に多く、37℃程度の発熱、腹痛、嘔吐、下痢を伴い、下痢は1週間以上長引く事もあります。
治療は対症療法となります。
|
| 口腔ケア |
|
| 参考資料 |
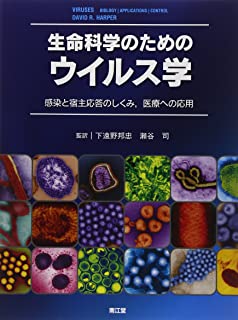 『生命科学のためのウイルス学―感染と宿主応答のしくみ,医療への応用』 『生命科学のためのウイルス学―感染と宿主応答のしくみ,医療への応用』
 『医科ウイルス学』 『医科ウイルス学』
 『新しいウイルス入門 (ブルーバックス)』 『新しいウイルス入門 (ブルーバックス)』
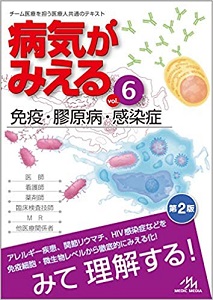 『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』 『病気がみえる vol.6 免疫・膠原病・感染症』
|
|









